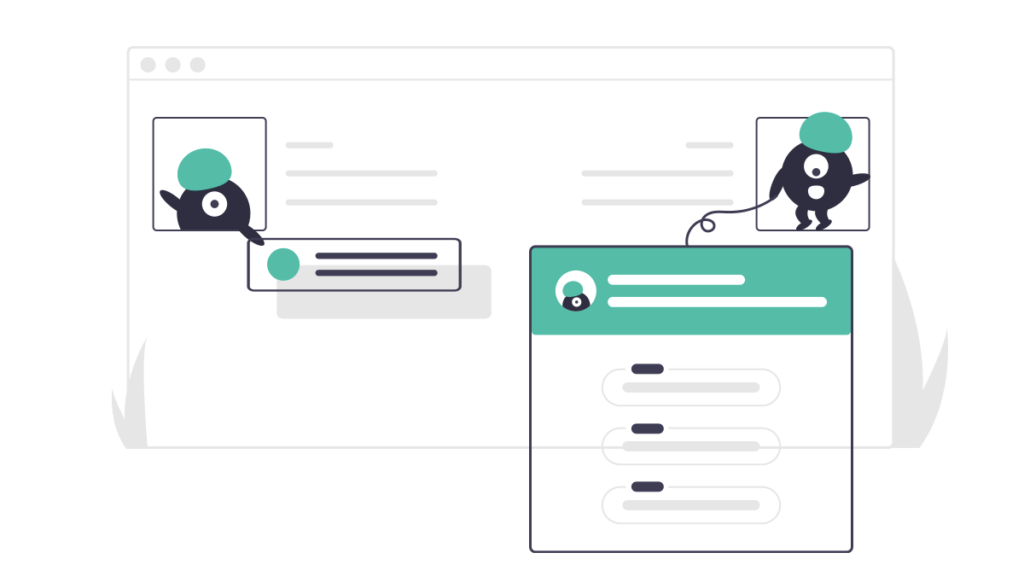業務効率化は現行の業務のやり方を見直すことで費用対効果・QCDの改善に取り組むことです。業務効率化と一口にいっても最適化すべき部分や方法は各企業の状況によって異なります。本記事では、業務効率化を実現するためのステップと手法・ツール、さらに成功のためのポイントをご紹介します。
業務効率化とは?
業務効率化とは、現行の業務から不要な部分の排除、非効率な部分を改善し、より高い生産性で業務を行えるようにすることです。つまり、「業務における費用対効果の改善」となります。取り組みの実態としては、費用(人的コスト・原料・期間)を削減して、効果(サービス・製品の質)は現状をキープする、という考え方で取り組まれる場合が多いです。
業務効率化によって得られるメリット
業務効率化のメリットを理解することで、ご自身で取り組む場合にもゴールや目的を適切に設定しやすくなります。享受できるメリットは、コスト削減も含めて以下が挙げられます。
- 人的コストの削減: 業務を担当する人数の削減、業務あたりの作業工数削減
- 作業期間の短縮: 作業開始から完了までに必要な時間・期間が短くなる
- ミスの削減: 対象業務における作業ミス、抜け漏れ遅れが減る
- 業務品質の安定: 業務の対応やアウトプットが安定する
- 従業員満足度向上: メンバーへの作業負荷が軽減され、働きやすい環境になる
業務効率化におけるゴールの考え方について
上記のメリットを理解した上で、ご自身の業務にどのように活かすべきか、業務効率化に取り組む際のゴールとポイントについてご説明します。業務効率化は対象業務のQCDのいずれか、または複数の要素を改善することが目標として設定されます。QCDは業務品質の指標でそれぞれ以下3つの観点を表しています。
- Q: Quality(品質): 業務のクオリティ、成果物の品質、作業のミスの少なさ
- C: Cost(費用): 人件費、原料費、コミュニケーションなどのあらゆるコスト
- D: Delivery(納期): 作業を開始してから完了するまでのリードタイム、所要時間
QCDの考え方はQCDの概要と活用方法についてまとめた記事でも詳細をご紹介していますので、合わせて参考にしてください。
業務効率化に取り組む流れとポイント
業務効率化に取り組む場合のステップと、ステップごとのポイントについてご紹介します。一見、遠回りに見えますが、正しい手順を踏むことでより効果的に業務効率化を実現できます。場当たり的な効率化のアイディアを実行するのではなく、入念に計画を立ててから着手しましょう。
1. 現状把握と業務選定
業務効率化の最初のステップとして、現状把握と業務選定を実施します。最も重要な作業と言っても過言ではありません。現状把握は現在の業務の可視化・見える化をすることで、業務実態を把握し、特に効率化が必要だと思われる業務を見極めることを目的とします。まず、対象となる業務の候補を洗い出し、それぞれについて作業実態を明らかにします。
現状把握の方法としては、現場への業務ヒアリングが有効です。主に以下の内容を確認することで実態を明らかにします。
- 各業務の目的とゴール
- 一連の業務フロー
- 具体的な作業内容(担当者名、作業の手順、使用するツール、所要工数)
- 業務に対して感じている不満、要望
ヒアリングの方法について詳細を紹介した記事がありますので、合わせてご確認ください。
ヒアリング結果はサマリーとして定量的にまとめるようにしましょう。
ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。
2. スコープ・目標・期間を決める
業務効率化に取り組む「計画」を最初に明確にします。前述の業務効率化の「メリット」「ゴールの考え方」の2点を確認しながら検討してください。「スコープ・目標・期間」のそれぞれの要素について説明します。
スコープ
業務効率化の対象となる業務の範囲です。ここでは作業の範囲と合わせて、業務効率化の施策対象になる担当者・関係者も明らかにします。
目標
目標は可能な限り定量的な内容で設定しましょう。例として良い目標設定と悪い目標設定のサンプルを記載します。
悪い目標設定
- 業務で発生しているミスを減らす
- 作業にあたっているメンバーの負荷を軽減する
- 業務の品質を安定させる
良い目標設定
- ミスの平均発生件数を現在の10件/月から3件/月まで軽減する
- メンバーの一人あたりの作業工数を20%削減する
- 1件あたりの開始から完了までにかかる時間を5時間短縮する
目標設定をする際に、目標数値を定量的に設定できない場合は再度、現状把握から取り組んでください。
期間
業務効率化に取り組む期間を明確にします。断続的・継続的に業務効率化を実施する場合も、前項で設定した目標をいつまでに達成するのかは必ず設定しましょう。一般的な業務効率化のプロジェクトでは3ヶ月単位で設定される場合が多いです。
3. 業務効率化へ着手
計画を立てたら業務効率化に取り組んでいきます。業務効率化の具体的なアプローチについては後述します。当然ですが、立てた計画は実行に移さなければ意味がありません。
業務に取り組むメンバーが複数名いる場合は、現場の協力が必要不可欠になります。状況に応じて、対象者に説明する場を設けましょう。業務効率化は本来、現場のメンバー・関係者にとってもメリットがある内容なので、背景や目的を丁寧に説明することで協力を仰ぎやすくなります。
4. 振り返りと効果測定
振り返りは最後だけでなく、定期的に実施することが重要です。業務効率化のプロジェクトの期間次第ですが、3ヶ月以内のプロジェクトであれば週1回または隔週で、3ヶ月を超えるプロジェクトであれば月1回を最低限の振り返り頻度の目安と考えてください。
また、振り返りには現場のメンバーにも同席してもらうようにしましょう。目標として設定した定量的な指標に近づけているかの確認と合わせて、現場での負担や問題などの定性的な状況についても確認しましょう。
ビジネスシーンで活用できる振り返り手法は複数存在しますので、振り返り手法を特徴ごとにまとめた記事を参考にしてください。もし、振り返りに不慣れな場合はKPTのフレームワークに従って実施すると良いです。
業務効率化に取り組む場合の注意点
業務効率化に取り組む中で以下の点について注意してください。特定の改善活動を進めるなかでも俯瞰的な視野で全体最適に意識を払うことが重要です。
現場の混乱などにより品質の低下を招いてしまう
業務効率化では既存の業務フロー・業務プロセスを変更する場合が多くあります。新しい施策において実現可能性が考慮されていないことや、業務を理解していないメンバーが改善活動を実施してしまうことで現場の混乱を招き、作業品質の低下を招いてしまう場合があるのでご注意ください。
他の部署や関係者への影響を考慮できていない
あらゆる業務は特定のチームだけでなく、作業に関わる前後の関係者や部署によって進行されています。業務の一部を変更するだけでも、前工程・後工程を担当する部署に影響があることを忘れないようにしましょう。業務改善の具体的な施策を考える際に、俯瞰的な視野を持つことが重要です。
業務をいきなり大きく変えてしまう
業務効率化の活動の中で業務プロセスを変更する場合、「小さい規模で試験的に運用する」ことを意識してください。よくある失敗として、計画を立てたら試験的な実行もせずいきなり大幅に業務を変更してしまうケースがあります。そうすると想定外の事象の発生や、そもそも新しい方法自体が不慣れな結果、ミスが多発して想定していた効果が得られないといったことに繋がります。どのような種類の変更であっても、可能な限りは必ず試験的な運用や小さく始めることを意識してください。
ゴールや目標の設定があいまいなまま進めてしまう
実際の現場では業務効率化の活動を見切り発車で初めてしまうケースが少なくありません。特に、トップダウンで「業務効率化を進めるように」と司令があった場合は注意が必要です。どのような形で業務効率化に取り組む場合も、必ず前述の「スコープ・目標・期間を決める」のステップは踏むようにしてください。
継続的な効果測定が実施されない
業務効率化の活動が完了した後、成果を測るために効果測定を実施しますが、その後も継続的に効果測定をし続けることが重要です。事業環境は常に変化し続けていますので、定期的に事業パフォーマンスを定点観測するようにしましょう。
業務効率化に使える具体的な手法
業務効率化を実現するための具体的な手法をご紹介します。最初に費用をかけることなく取り組める業務上のプロセス変更や施策を中心に記載します。
業務の定型化・標準化による効率化
業務の方法や取り組む流れをある決まった形に整理して、チームで取り組み方を統一します。企業で取り組まれている業務の多くは、それぞれの担当者が任意の方法で都度、対応していることが多いです。
一見、定型化、標準化が難しい業務に思えても、冷静に見てみると同じやり方に統一できる場合が少なくありません。定型化、標準化が可能かどうかを判断する要素には以下があります。
- 繰り返し発生している業務か
- 業務の流れをマニュアル化することができるか
業務を定型化、標準化することで、安定した業務品質を実現できるだけでなく、メンバーの増加や入れ替わりなど担当者が変わった場合でも、素早く同じクオリティで業務を実施できるようになります。また、業務の流れが明確になるため、進捗状況の管理も容易になり、ミスや抜け漏れの防止に繋がります。
ムダムリムラを発見して改善策を考案
業務の非効率さを生み出す指標で、3Mと呼ばれる場合もあります。言葉のままですが、「ムダ」は不要な作業や過剰なリソース、「ムリ」は作業量とリソースの不一致、「ムラ」は作業量やリソースの不安定さを表します。課題発見のために以下の観点で現在の業務を確認しみてください。
- ムダ: 不要な作業・人員を過剰に投下している・設備やツールが活用できていない
- ムリ: 作業量の超過・人員不足、短納期・過剰な品質
- ムラ: 作業量の不安定さ・作業人員の不安定さ
この指標は実際の業務効率化を考えるうえでも役立ちますが、現状分析をする際に、どこに改善できるポイントが存在するかを見極める上でも有用な考え方です。
ペーパーレスによる情報共有の円滑化
稟議や帳票、記録、契約など業務において紙を使う場面は多く存在するかと思います。しかし、改めて検討してみると、実物の紙が必要なく、電子化できることがほとんどです。ペーパーレスを実現する上では、具体的な取り組み方がいくつか存在します。
- ワークフローシステムなどツールの導入
- 紙をスキャンして、PDFとして保管
- WordやExcelなど記録先を電子化
業務において、いきなりすべてを電子化するのはハードルが高いかと思います。最初にペーパーレスに着手するうえで、おすすめの取り組みとしては「保管」の電子化です。稟議や業務記録など、紙媒体で実施して完了したものを、スキャンしてPDF化してオンラインストレージ等に保管します。紙利用の最後のプロセスですが、この部分を電子化するだけでも、保管場所の削減、索引性の向上、共有性の向上など様々なメリットが見込めます。
アウトソーシングによるリソースの最適化
自社の業務の一部を外部に委託する方法です。BPO(Business Process Outsourcing)と呼ぶ場合もあります。アウトソーシングといっても規模は様々で、小さな規模であれば単純作業をクラウドソーシングで委託したり、オンライン秘書を活用したり、といったことから活用可能です。大きな規模になると、バックオフィス業務の部門をまるごと外部企業に委託するという場合もあります。
アウトソーシングのメリットは、自社のコアの業務以外を外部にお任せすることで、競争優位性を高めつつ業務効率化を推進できることです。また、一般的には、外部委託によるコスト削減という認識が強いですが、対象業務を専門家に任せることで、業務品質の向上が期待できる場合もあります。
注意点として、標準化されていない業務のアウトソーシングは、体制構築までの準備・設計のハードルが高く、最終的なコストメリットの実現に時間がかかることです。アウトソーシング先とのコミュニケーション、連携が肝となることをご認識ください。
会議のオンライン化によるコミュニケーション円滑化
リモートワークの推進も伴って、会議をオンラインで実施するケースが増えています。オンラインでの実施は『Zoom』や『Skype』などのツールを利用する場合が多いです。
オンライン会議はメリットだけでなく、デメリットも存在しますので、特徴を理解した上で、適切に取り入れると良いでしょう。
オンライン会議のメリット
- 移動時間が不要となるため、会議前後のムダな時間が削減できる
- 場所や時間の制約を受けづらい
- 画面共有など、一部の用途によっては対面の会議よりコミュニケーションがしやすい
オンライン会議のデメリット
- 初対面の場合、会話のリズムや雰囲気が掴みづらい
- 発言者は常に1人でないと聞き取りづらい
- 対面よりも気軽なため、不要な会議やMTGが設定されてしまう
オンライン会議は人数がそれほど多くなく、関係構築が既にできているメンバー同士での実施に向いています。ぜひ、上手く使い分けてください。
ECRSを用いた改善を通じて業務効率化
ECRSは業務改善に取り組む際に用いられるフレームワークです。業務を見直すための以下4つの観点の頭文字を合わせたもので、「イーシーアールエス」または「イクルス」と読みます。
- Eliminate(排除): 業務やプロセスをなくす
- Combine(結合) : 別々の作業を同時に処理する、ひとつにまとめる
- Rearrange(再配置): プロセスや担当者を入れ替える
- Simplify(簡素化): 手順やプロセスを簡単なものに変える
並び順の、E→C→R→Sは改善効果の大きい順に並んでいます。この流れで業務の見直しを行うことで、効率的に業務改善に取り組むことができます。
ECRSを通じた業務改善の具体的な方法と流れをまとめた記事がありますので、ぜひ参考にしてみてください。
業務マニュアルを整備して作業の理想形を明確化
業務マニュアルの作成も、業務効率化に役立てることができます。マニュアルを作成することで業務の属人化を防ぐだけでなく、作成の過程でどのような流れが、理想的な手順なのかを考えることに繋がるので、業務の平準化、業務品質の安定も期待できます。
マニュアル作成は、事前準備や作成した後のメンテナンスのポイントになります。詳細はマニュアル作成のコツとポイントをまとめた記事で紹介していますので、合わせて確認してみてください。
フローチャートを作成して業務を包括的に理解する
業務マニュアルとも類似しますが、フローチャートを作成することで、現状の業務プロセスを明確にし、業務効率化につなげることができます。
ただ、業務マニュアルと比較すると、作業で実際に活用するというよりも業務理解・業務整理のための把握、という側面が強いので、状況に応じて使い分けてみてください。
フローチャートは業務全体の流れを図解したもので、包括的・抽象的に業務を把握する場合におすすめです。作成に必要な工数も、作業手順書と比較すると多少楽なものになります。
フローチャートを実際に作成する場合は、フローチャートの作成方法と詳細をまとめた記事がありますの、参考にしてください。
作業手順書で業務の詳細と各論を理解する
作業手順書は、特定の業務の作業一つ一つの手順について詳細にまとめたものになります。作成の工数は多くかかりますが、より詳細かつ深く業務を理解することができます。
作業手順書を作成する場合は、作業手順書の作成方法と詳細をまとめた記事がありますので、参考にしてください。
スキルマップを作成し人員配置を適材適所に
スキルマップは、業務進行において必要なスキルを一覧にした表のことです。評価基準に沿ってメンバーごとにスキルを記入していくことで、1人ひとりの現状のスキルを見える化することができます。
スキルマップを作成することで、適材適所に人員を配置できるようになります。当然、一人あたりの生産性が向上するので、組織全体として業務効率化を実現できます。また、スキルマップを通じてメンバーの得手不得手を理解することで人材育成にも繋げられます。副次的なメリットも多いので、ぜひ活用を検討してみてください。
実際に作成する場合は、スキルマップの作り方を手順ごとにまとめた記事がありますので参考にしてください。
ドキュメントの雛形作成による品質向上
ドキュメント作成は業種・業界に関わらずあらゆる業務で発生します。例えば、営業チームにおいては、クライアント様に合わせた提案資料や、契約後のオンボーディング資料など、ドキュメントは欠かせません。ドキュメント作成は各種業務の中でも工数がかかり、スキルによって品質に差が出やすいものの一つです。
業務効率化のために、頻繁に作成するドキュメントは事前にひな形を作成しておくことをおすすめします。
雛形を作成することで、都度発生する工数を最小化することが可能になるだけでなく、作成されるドキュメントの品質も担保しやすくなります。
業務の優先順位を明確化しタイムマネジメントを徹底
タイムマネジメントは、より生産性が高い業務にリソースを集中させることで、業務効率を高めて組織としての生産性を向上できます。タイムマネジメントの実施にあたっては、業務の洗い出しと、優先順位の明確化が必要不可欠です。
具体的な業務の例を四象限に当てはめると以下のような形です。
- 重要かつ緊急…顧客対応、事業計画の策定
- 重要だが緊急でない…業務改善の取り組み、マニュアルの整備
- 重要ではないが緊急…電話応対、資料作成、印刷などのオペレーション
- 重要でも緊急でもない…デスクや棚の整理、書類の廃棄
業務を上記の4つに分類して①→②→③→④の順番で対応していくことで、取り組むべきものから着手できます。
タイムマネジメントに取り組む場合は業務分類の方法・マネジメントの方法の詳細をまとめた記事をご確認ください。
メンバーの教育による生産性の底上げ
短期で成果を出すことは難しいですが、チームメンバーの能力を向上させることで、業務効率を向上する方法もあります。メンバーの能力向上は、既存メンバーがより良く業務を遂行できるようにレベルアップさせたり、新規メンバーが早期に立ち上がれるようにドキュメントや教育体制を拡充したり、複数のアプローチが存在します。
特に、担当するメンバーが流動的だったり、入れ替わりが激しい業務においては「業務についての知識がまったくない人がどれだけ早く、安定して作業に取り組めるようになるか」が競争優位性においても重要です。
現在のチームの状況を把握したうえで、業務効率化に繋がりそうなメンバーの能力向上施策がないか、検討してみてください。
進捗管理・進行管理の徹底
プロジェクト形式の業務を効率的に進めるうえで、進捗管理・進行管理は必要不可欠です。進捗管理は「プロジェクトの目標を達成するために、計画どおりに業務が進むようマネジメントすること」です。
進捗管理によって、業務効率化はもちろん、チームメンバーのパフォーマンス最大化や、問題の早期発見など、様々なメリットが享受できます。
進捗管理の具体的な取り組み方法をステップごとに説明した記事がありますのでご参考ください。
業務効率化に使えるツール
ここでは業務効率化に有効なツールやソフトウェアをご紹介します。有料のものも存在しますが、業務内容によっては費用対効果も得られますので、ぜひ検討してみてください。
RPAによる単純作業の自動化
人手で実施している作業をロボットやシステムが自動で実施するように置き換える方法です。RPAは「Robotic Process Automation」の頭文字を取った略称で、人が実施するパソコン操作のうち、決まった手順で実施されている操作をロボットが自動で実行するものです。例えば、帳票の入力やデータの転記作業など、繰り返し大量に実施する操作を代替するのに適しています。
RPA化のメリットとして、業務効率化・費用対効果の改善はもちろん、人と違って24時間働くことができ、ミスもしない、ということが挙げられます。日本では『UiPath』『WinActor』といったツールが有名です。導入ハードルはやや高く、RPAを構築するためには知識が必要となるため、時間をかけて学習するか、社外の専門家に依頼する必要があります。
クラウドストレージ導入による情報共有と紙の廃止
クラウドストレージとは、データを格納するためインターネット上の仮想スペースです。パソコン内のハードディスクや社内のファイルサーバーを利用せず、インターネット上にデータを保管することができます。主要なサービスだと『Dropbox』『Box』『Google Drive』などがあります。
クラウドストレージを活用することで、デバイスに関わらずいつでもデータにアクセスできるようになり、任意のメンバー同士でのデータ共有もカンタンになります。ただし、企業によっては、外部のクラウドストレージにデータを置くことを禁止している場合もありますので、利用を検討される際は、社内規定等を確認するようにしてください。
プロセスマネジメントツールで定型業務を効率化
作業の流れや担当が決まっている定形業務のマネジメントにはプロセスマネジメントツールが有効です。作業の流れを見える化して管理できるだけでなく進捗状況をリアルタイムで管理できるため、ミスや抜け漏れを防止し、業務効率の改善に有効です。
弊社が開発している「octpath」も、あらゆる業務をフロー形式で管理できるプロセスマネジメントツールです。
フローに沿ってマニュアルやチェックリストを管理できるため、octpathに沿うだけで誰でも同じように作業を進めることができます。また、リマインドやアラート機能、作業記録機能により、ダブルチェックや作業の確認・報告などの管理コストを削減できます。サービスサイトより、ぜひ詳細を確認してみてください。
ワークフローシステムによるコミュニケーション円滑化
ワークフローシステムは、業務プロセスをシステムで管理することによってミスや抜け漏れを減らし業務進行を円滑にすることが可能です。
日本国内において、ワークフローシステムは「電子稟議」を指す場合もあります。従来、紙とハンコで承認・決済を行っていた稟議フローをシステムに置き換えるものです。ただし、本来のワークフローシステムは承認や決済のプロセスだけでなく、作業を含んだ業務プロセス全体をマネジメントするためのシステムを表します。
もし、対象の業務が以下の特徴に該当する場合は、ワークフローシステムの活用を積極的に検討してみてください。
- 業務のプロセス、フローが定型化されている
- 複数人のメンバーや部署が連携して業務を進めている
- 繰り返し発生する業務である
グループウェアを活用して事業全体をマネジメント
グループウェアは社内の情報共有ツールです。スケジュール管理、ファイル共有、タスク管理など業務に必要な様々な機能が一つにまとまっていることが特徴です。業種・業界問わずに活用可能な機能が網羅的に搭載されているので、業務効率化の最初のシステム導入として検討するもの良いでしょう。『G Suite』などのサービスが存在します。
チャットツールでメールよりもきめ細かいやり取りを実現
メールに代わるコミュニケーションツールです。チャットはメールと比較した場合、より気軽に双方向のコミュニケーションが実現できます。特にチーム内で細やかな情報連携、外出先からのやりとりにおすすめです。『Slack』『Teams』『Chatwork』『LINE Works』などのツールが代表的です。
プロジェクト管理ツールを用いてプロジェクト全体を管理
プロジェクト形式の業務におけるタスク管理や進行管理に活用できるツールです。ガントチャートやタスクの一覧、メンバーごとの作業状況、スケジュール管理など、プロジェクトの業務をマネジメントするためのあらゆる機能が搭載されています。
定型業務やルーティーン業務の管理には不向きですが、逆にタスクやスケジュールが流動的な場合に役立ちます。『Asana』『ClickUp』『Wrike』などのサービスがあります。
Wikiツールを活用して社内のナレッジを共有
社内の情報共有やナレッジの管理に活用できます。Wikipediaのように、各テーマごとにページを作成して、社内情報を記録、アップデートできます。また、マニュアルの記録先として作業手順などを記載・管理するために活用される場合もあります。
大変便利なツールですが、情報更新のルールや風土が正しく組織内で醸成されていないと、一度登録した情報が形骸化してしまう場合もありますので、ご注意ください。『Confluence』『Notion』『esa』などのサービスがあります。
マーケティングオートメーションで営業を効率化
マーケティング向けの業務改善ツールになります。マーケティングオートメーションツールは「MA」と呼ばれることもあり、一言でいうと「顧客開拓におけるマーケティング・営業活動を可視化、自動化するためのツール」です。見込み顧客のステータスに合わせて最適なアプローチの実施、さらにはマーケティング・営業コストの低下が見込めます。国内外から様々なツールが出ており『マルケト』や『b→dash』などが有名です。
サービス同士の連携を自動化するiPaaS
iPaaSは「アイパース」と読みます。「Integration Platform as a Service」のそれぞれの単語の頭文字をとった略称です。なかなかイメージが湧きづらい内容ですが、端的に説明するならば異なる複数のツールやサービス(一般的にはWebサービス)同士で情報を連携したり、統合したりできるものになります。例えば「新入社員の情報をサービスAに登録すると、チャットツールBで関係者に連絡が自動通達される」といったことが可能になります。複数のサービスをiPaaSを用いて統合することで、二度手間を解消し、作業の抜け漏れの防止、費用対効果の改善などが見込めます。有名なサービスでは『IFTTT』や『Zapier』が存在します。
SFAやCRMで営業活動の業務改善と受注率の向上を実現
営業向けの業務改善に繋げられるツールです。SFAは「Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)」の頭文字をとった略称で、日本においては営業支援ツールとして認知されています。顧客ごとの対応やネクストアクション、報告状況などを管理できます。さらに、SFAは営業チームの情報や業務の自動化・分析により業務の効率化を支援します。また、SFAと並んでCRMもメジャーなツールで「Customer Relationship Management (カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)」の頭文字をとった略称です。国内だと顧客管理システムと呼ばれたりします。CRMは名前のとおり顧客管理に優れており、基本情報や属性、ステータスなど顧客に関わる内容を一元管理し、適切なマーケティングやセールスを支援してくれます。具体的なサービスでは『Sales Cloud』『Zoho CRM』などが有名です。
さいごに
業務効率化に向けた具体的な取り組みはイメージできましたでしょうか。まずは、ご自身の業務状況を把握した上で、適切な目標設定のうえ、業務効率化にチャレンジしてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。