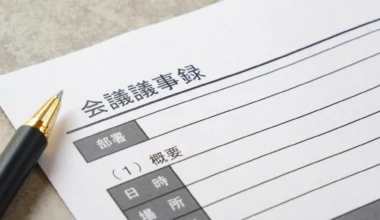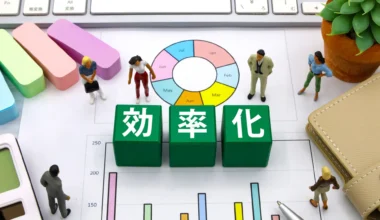業務改善に取り組むためには、現状の業務を正確に理解するための業務ヒアリングが不可欠です。この記事では、業務ヒアリングの基本的な5つのステップと、各ステップで意識すべきポイントをお伝えします。
ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。
業務ヒアリングの概要
具体的な手順を説明する前に、まずは業務ヒアリングの概要をご説明します。
3つのヒアリング方法
業務ヒアリングには、主に以下3つの方法があります。最適な方法はヒアリング対象となる作業内容や関係人数によって異なるので、業務の状況を踏まえて検討してみてください。
- 立会調査…現場に赴き、実際に作業を目で見て確認する
- ヒアリング…担当者から口頭で説明をうける
- 業務調査票の配布…調査票に作業内容を記入してもらい、紙面で確認する
実際には、いくつかの方法を組み合わせてヒアリングを進めることが多いです。特に業務調査票を利用する場合は、記入する作業の粒度やレベル感が回答者によって異なってしまうため、ヒアリングをしながら詳細を確認していくケースが一般的です。
また、作業内容を正確に文字に起こすのは思いのほか難しいため、業務内容に関わらず立会調査を行い直接業務を確認するのがおすすめです。現場の担当者にデモンストレーションしてもらうのも良い方法です。
ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。
最終的なアウトプットの形式
業務ヒアリングは、あくまでも業務改善のためのひとつのステップに過ぎません。ヒアリングした内容を以下のようなアウトプットにまとめ、そのアウトプットを活用して何某かの業務改善施策に取り組みます。
- 作業手順書…作業の具体的な手順を記載することで、業務の標準化につながる
- フローチャート…業務全体のフローを把握することができ、進捗管理に役立てられる
- チェックリスト…作業時に注意する観点が明確になり、ミスや抜け漏れを削減できる
どのような形式にまとめるかは、業務ヒアリングの目的や業務の特徴を踏まえて検討してください。それぞれ作成のイメージが湧かない・対象業務にとってどれが最適か分からない場合は、それぞれの概要と作成方法についてまとめた記事を参考にしてください。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。



ヒアリング対象者の選定と調整の方法
業務ヒアリングを行うにあたって必要な、対象者の選定と調整の方法について解説します。
ヒアリング対象者の選定方法
当然ですが、基本的には業務に関わるメンバーがヒアリングの対象者となるため、作業ごとに一人ずつ担当者を選びヒアリングをしていきます。ただし、業務が属人化していると同じ役回りでも別の手順で取り組んでいる可能性があります。その場合は複数名にヒアリングをした方がより正確な情報を集めることができます。
また、業務ヒアリングでは「管理者」と「実際に作業を担当している人」の両方から情報を回収することがおすすめです。管理者・マネージャーは業務全体は把握できていても、業務の詳細が分からないことも多くあります。現場のメンバーにしか分からない情報が隠れていることもあるため、作業担当者から一次情報を聞き出すことが理想的です。
ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。
調整の方法
業務ヒアリングの実施方法は、以下の2つのパターンがあります。
- 一度に全員を集めるパターン
- 一人ずつに対してヒアリングをするパターン
業務の特徴や業務時間によって適切な方法は変わりますが、関連メンバー全員を集めることは難しいため、少人数で分けて実施することが一般的です。ヒアリングの終了期限を定めた上で、期限までにそれぞれと日程調整をした上で実施してください。
業務ヒアリングは、ヒアリングの実施者も対象者も通常通り業務を進行しながら対応する必要があります。多忙な曜日や時間帯をずらすなど、通常業務を圧迫しないよう注意しながら日程調整を進めましょう。
また、業務ヒアリングをスムーズに進めるためには、担当メンバーの協力が不可欠です。取り組みの概要や目的などを具体的に伝えておくこともポイントです。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
業務ヒアリングの具体的なステップ
ヒアリング対象者との調整が済んだ後、実際の業務ヒアリングは以下の5つのステップで進めていきます。この章では各ステップの具体的な手順とTipsをご説明します。
- 目的の明確化
- ヒアリングする情報の洗い出しと、情報回収シートの作成
- 現場担当者に業務詳細をヒアリング
- ヒアリング内容を確認し、まとめる
- 担当者からフィードバックを回収
1. 目的の明確化
基本的なことですが、業務ヒアリングの質を決める重要な部分です。業務ヒアリングの目的は、業務フローの改善・人員の最適化・業務の標準化など様々であり、それによってヒアリングすべき情報が変わります。必要な情報を無駄なく効率的に回収するために、目的を再度確認しておきましょう。
2. ヒアリングする情報の洗い出しと、情報回収シートの作成
目的が明確になったらヒアリングしたい項目を決め、それらを記入するためのシートを作成します。情報回収シートは担当者ごとに作成して配布する想定で、以下の画像のように、ヒアリングしたい項目を横軸に、作業内容を縦に時系列順に記入していくイメージです。

ちなみに、サンプルシートは以下のボタンからexcel形式でダウンロードしていただけます。そのまま雛形としてご活用いただいても構いませんので、参考にしてみてください。
ヒアリングすべき項目は、例としては主に以下のようなものがあります。
- 各業務の目的とゴール
- 一連の業務フロー
- 具体的な作業内容(担当者名、作業の手順、使用するツール、所要工数)
- 業務に対して感じている不満、要望
- 業務の発生タイミング
- 各業務の意味や背景
ポイントは、業務内容だけでなく、各手順の意味や背景についても確認することです。改善点を考える際の参考にするため、また、業務進行において変更できない箇所がある場合に把握しておくためです。
ただ、項目は前章でご紹介したアウトプットの形式によって変わり、それに合わせてシートの形式も変わります。例えば、フローチャートを作成するのであればざっくりとした作業を把握できれば良いですが、作業手順書やチェックリストなら作業手順の詳細まで聞き出す必要があります。
サンプルでは、以下の赤枠の項目に該当します。解決したい課題に合わせて、項目や粒度を調整してみてください。

また、ヒアリングする項目を決めるためには、対象業務の大枠を把握しておく必要があります。業務のイメージがつかない場合は対象業務の管理者に事前にヒアリングを行い、全体像を掴んでからシートを作成することをおすすめします。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
3. 現場担当者に業務詳細をヒアリング
実際に作業担当者から情報を回収します。業務ヒアリングをするときにも、ヒアリング先の担当者は通常通り作業を進めなければなりません。できるだけ負担をかけないよう、以下のような工夫をしながら進めましょう。
- 業務で使用しているマニュアルや資料を共有してもらい、事前に読み込んでおく
- 複数名が連携して作業をしている場合には、一括してヒアリングする機会を設置する
- 書面で回答してもらった後、疑問点のみを口頭で確認する
ヒアリングの精度の目安として、ヒアリング内容をもとに「自分が全く同じように業務を進められるか」を考えることをおすすめします。それくらい、対象業務について具体的に、深く理解することが重要です。
ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。
4. ヒアリング内容を確認し、まとめる
担当者からヒアリングした情報を確認し、作業手順書やフローチャートなどの形式にまとめていきます。情報を確認する際には、集めるべき情報に抜け漏れがないかはもちろん、フロー全体と各作業間でも齟齬がないかを意識してください。例えば、全体のフローにはダブルチェックのステップが存在しているが、実際には省略されており誰も作業をしていなかった、などです。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
5. 担当者からフィードバックを回収
完成したら、実際の作業と齟齬がないかをヒアリング先の作業担当者に確認し、フィードバックを回収します。フィードバックの回収・修正の流れを繰り返すことで、情報の精度を上げていきます。可能であれば、この流れを3周ほど繰り返せると理想的です。
作業者と共通の認識を持てたら、完成となります。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。
ヒアリング時のポイント
ヒアリングの回数と時間について
ヒアリングの方法は、基本的に担当している業務の性質や雰囲気に合わせて調整していただければ構いませんが、弊社では以下のような進め方を推奨しています。
通常2-3回のヒアリングが必要
1回のヒアリングで全ての情報を確認しきることが理想的ですが、実際に1回で終えられることはほとんどありません。確認漏れがあったり、ヒアリングを進めていく中で知らなかった作業が出てきたりするケースもあるため、少なくとも2回以上やり取りが発生することを想定しておきましょう。
極力短時間でヒアリングできるよう工夫する
前述しているように、業務ヒアリングは通常業務にプラスアルファとして対応する必要があります。業務を圧迫しないよう、ヒアリング時間はなるべく短く抑えるように意識しましょう。通常時のミーティングや打ち合わせと同様、30分〜1時間を目安に考えておくと良いかと思います。
また、ヒアリングを短時間で終えるため、以下の準備をしておくことをおすすめします。
- ヒアリング事項を洗い出しておく
- 可能であれば事前に対象者に伝えておく
- 業務の関連情報がまとまった資料があれば共有してもらう
抽象的な情報にならないように
目的次第ではありますが、ヒアリングする情報は抽象的になりがちです。作業担当者と共通認識を持てるよう、できる限り具体的に聞くことを意識してください。定性的な文言は避け定量的に記録するなどのほか、必要であれば画像や写真などの参考資料とともに残しておくこともおすすめです。
ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。
「実際に作業を担当している人」から情報を回収する
リーダーや管理者はあくまでもマネジメントをする立場なので、業務詳細を把握できていないことも多いです。実際に現場で作業を担当しているメンバーにしか分からない情報が隠れていることもあるので、作業担当者から一次情報を聞き出すことが理想的です。
ヒアリング内容をまとめる際はメモ程度から始める
実際の業務ヒアリングの場面では、一度でヒアリングを終えられることはほぼありません。はじめはメモレベルのヒアリングから始め、情報がある程度集まってからシートやドキュメントに成型していくと、修正の手間を減らすことができます。
おわりに
業務ヒアリングは業務改善のために不可欠なステップですが、きちんとポイントを押さえて取り組まなければ有益な情報は得られません。記事でご紹介した内容を参考に、是非ご自身で取り組んでみてください。
効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。