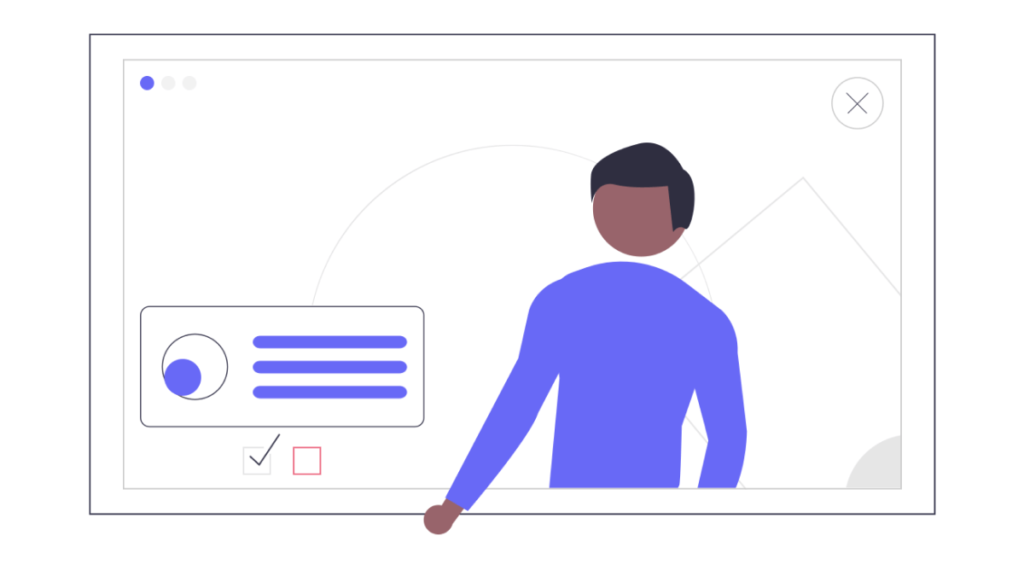業務委託は社外のリソースを活用して、自社だけでは対応できない業務に対応したり、専門家の力を借りたりする際の労働形態です。単純な人手の充足だけでなく、新しいスキルの獲得や、より生産性の高い業務体制の確立など様々なメリットや可能性がある取り組みです。
ただし、社外の人や企業との業務委託に関わる契約が必要となるので、トラブルを生まないためにも形式や注意点を理解しておくことが重要となります。
業務委託とは?
業務委託の意味と概要
業務委託とは、外部の企業や人に特定の業務遂行を委託することを指します。自社だけのリソースでは対応が難しい場合や、専門の知識が必要な業務を遂行するために活用する場合が多いです。
別の言い方で「アウトソーシング」と表現する場合があります。アウトソーシングも言葉の定義としては業務委託と似ていますが、業務委託よりも広義に「自社の業務の一部を外部に委託する取り組み」を指します。業務委託は委託先が個人(規模:小)、アウトソーシングは委託先が企業(規模:大)というニュアンスの相違でも使い分けがされています。アウトソーシングの詳細やメリットについてまとめた記事がありますので、合わせて参考にしてみてください。
企業が業務委託を活用するメリット
業務委託によって自社以外のリソースを活用することで様々なメリットを享受できます。
- 対象の業務におけるQCD(納期・品質・費用)が改善する
- 自社の中核ではない業務を委託することで社内リソース活用を最適化
- 対象業務を安価なコストで委託することで費用対効果を改善
- 急なリソースの増加に対応できる
上記のとおりメリットは複数存在しますが、業務委託の目的として現場で実際によく見られるケースは「人員不足をまかなうためのリソース確保」か「専門的な業務の対応ができる人員の獲得」の2つのケースが多いです。
業務委託の契約形態について
「業務委託」という言葉自体は非常に浸透していますが、実は「業務委託契約」という名称の法律はありません。業務委託契約は民法に記載されている「請負契約」(民法 第632条)、「委任契約」(民法 第643条)などを根拠に取り扱われています。
実際の現場で交わされている業務委託契約は業務内容や目的に応じて内容が多岐に渡ります。双方で契約を締結したあとにトラブルや認識の齟齬を生まないためにも、契約内容を細かく決める必要があります。
請負契約について
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
「民法第632条 – 請負 」 金子総合法律事務所
請負契約は、「請け負った仕事を完成させる」「仕事の結果に対して報酬を支払う」と規定しています。つまり、業務を委託された企業や個人は、仕事を完成させる必要があるうえ、成果物に対しての責任を負うことになります。成果物に瑕疵やミス、不具合が見つかった場合には修正を求められることはもちろんのこと、損害賠償や返金を求められる場合があることに留意する必要があります。対象業務としては、以下のようなものが考えられます。
- デザイン業務(ロゴやアイコン、名刺などの作成)
- メディアの記事制作業務
- 動画の制作や編集業務
委任契約(準委任契約)について
「委任契約」には「準委任契約」というものもあり、「準委任契約」は受託対象の業務が法律行為ではない場合に規定されます。一般的な企業の業務は「準委任契約」に該当するケースが多いです。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
「民法第643条 – 委任」 金子総合法律事務所
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
「民法第656条 – 準委任」金子総合法律事務所
委任契約(準委任契約)では、求められる対象が「行為の遂行」だけで、成果物に対しての責任は発生しないことが特徴です。期間内に成果物が完成しない場合や完成した成果物の質が低い場合にも責任を持つ必要がないということになります。委任契約を行うケースとしては、例えば以下が考えられます。
- 経理業務のアウトソーシングをする場合(経理に関わる業務を全てお任せする)
- 支店の経営を代表に任せる場合
委任契約と準委任契約の違いは法律行為の有無
委任契約は法律行為を含む業務を委託する場合、準委任契約は法律行為以外の業務を委託する場合に締結します。例えば契約手続きは委任契約、事務作業や調査・リサーチの依頼を行う場合は準委任契約を利用します。一般的には準委任契約の方が多く用いられています。
契約にあたって意識すべきこと
前述のとおり業務委託のベースとなる契約形態「請負契約」「委任契約(準委任契約)」の違いは「成果物の完成及び完成した成果物に対して責任を負うかどうか」になります。一概にどちらで契約すべきということは難しく委託する業務性質や双方が合意できる内容かどうかという点が重要になります。双方が契約形態を決める上で根幹となる内容なので、どちらの形態で取り決めを交わすのか最初に検討しましょう。
派遣契約との違い
参考として、業務委託契約と類似した契約形態である「派遣契約」との違いも簡単にご説明します。
両者の一番の違いは雇用主にあります。業務委託の場合は委託先企業が業務担当者の雇用主となりますが、派遣契約の場合は派遣元の企業が業務担当者の雇用主となります。派遣契約の場合は、派遣元の企業と委託先の企業間で業務に関する契約を取り交わすためです。
それによって、成果物に対する責任の主体と指揮命令の主体が異なります。
| 業務委託契約 | 派遣契約 | |
|---|---|---|
| 雇用主 | 委託先企業 | 派遣元企業 |
| 成果物の責任 | 本人 | 派遣元企業 |
| 指揮命令の主体 | 不在 | 派遣元企業 |
成果物の責任は、制作した納品物等に不足やミスがあった場合に誰が責任を負うか、指揮命令は作業中の現場での指示や監督を誰が行うのかを表します。
派遣契約の場合は派遣先の企業が中間に立っているため、あくまでも派遣先の企業がどちらも担います。一方で業務委託契約の場合は、本人と委託先企業の直接契約となるため、成果物の責任は本人が負い、指揮命令を行う主体はいないという扱いになります。
業務委託を実施するまでの流れ
業務委託を活用する際の具体的な流れについて記載します。基本的にコストが発生する取り組みのため、検討部分も重要となります。そもそもの必要性の判断から、何を依頼するのかを含めて以下の流れで取り組みを進めてください。
1. 業務委託の必要性について検討
最初にそもそもの必要性を検討します。一度、業務委託を開始してしまうと途中での契約解除は信用毀損やサンクコストの発生などの面も含めてデメリットが非常に大きいです。対象の業務について業務委託を活用せずに対応できる方法が無いか、以下の観点で検討してください。
- そもそも廃止できる業務ではないか
- 別の既存業務を削減して生まれる人員リソースで対応できないか
- 別部署や関連会社で対応できる方法はないか
- ソフトやツールを導入することで自社で対応できないか
- 業務全体を最適化することで対応できないか
更に、詳細な業務効率化のアイデアについてまとめた記事もありますので合わせて参考にしてください。記載されているいずれの方法でも対応が難しく、外部への業務委託が必要と判断された場合に検討を進めていきます。
2. 業務委託の要件について整理する
具体的に委託したい業務の要件について整理します。多くの企業でこのステップを割愛してまうケースが散見されますが必ず実施するようにしてください。業務委託の要件を整理することで社内での認識統一に活用できるだけでなく、委託する際の選定基準も明確になるうえに提案をする受託側もスキルセット等を明確に説明できるようになります。具体的には以下の観点で要件を整理してください。
- 予算
- 依頼する業務の範囲
- 業務を委託する期間
- 必要なリソースのボリューム(人数 x 稼働率)
- 依頼する成果物
3. 求めるスキルセットを明確にする
業務委託の要件が明らかになったら、委託する人や企業における詳細なスキルセットについて検討します。こちらも依頼する業務の内容や自社のリソースの状況によって最適解がバラバラなため、全体を把握したうえでの整理が必要です。わかりやすい観点だと「委託予定の業務における実績や経験を求めるか」「資格を持っている必要があるか」などが該当します。もし、余裕があれば現在の自社のリソースと必要なスキルについて可視化した「スキルマップ」を作成することも有効です。
スキルマップの作り方についてまとめた記事もありますので、合わせて参考にしてください。
4. 業務委託先を探して選定する
対象の業務についての業務要件とスキルセットが明らかになったら実際に業務委託をする先の候補を見つけ出し、選定します。探し方は規模や対象の業務によりますが、以下の2つが主流です。
インターネットで探す
Google等で検索をかけたり、フリーランスの一覧サイト、業務委託を受けている企業のマッチングサイトなどを活用する方法です。広く、瞬時に候補を探すことができる反面、玉石混交のため実際の委託先を選定する際には目利きが大変であるというデメリットがあります。
知人や取引先の企業に相談して探す
関係者に紹介してもらうケースです。効率はよくありませんが、自社の特徴や状況を理解してくれている関係者からの紹介であれば信頼度も高く、フィットした委託先が見つかる可能性が高いです。知人を介しているリスクとして双方の関係性がゆるくなりやすいので注意してください。
いずれの探し方をする場合も、必ず複数名・複数社を候補として探すようにしましょう。依頼する業務内容によっては難しい可能性もありますが、短絡的に即断即決してしまうと最適な委託先を逃す可能性があります。また、相対的に良い委託先を判断するのにも有効です。
実際の選定の際には、事前に検討した業務要件とスキルセットを審査基準にします。もし、差し支えなければ候補の企業や人にもドキュメントを共有し、その内容に合わせて提案してもらいましょう。そうすることで、双方の認識齟齬を防ぐだけでなく委託先から対象の業務に該当する経験や実績の情報を共有してもらいやすくなります。
5. 契約を締結する
選定が完了したら契約書を交わして業務委託契約を締結しましょう。契約が完了したら実際に業務を開始していただくために必要な情報や設備を用意して業務の開始に備えます。
「偽装請負」とならないように注意する
書類上、形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを言い、違法です。
「あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?」 東京労働局
請負は、業務委託の使用者と受託者の間に指揮命令系統は発生しません。受託した側の責任と判断において業務を遂行します。偽装請負は契約上は委託契約にも関わらず、実態としては委託を受けている人・企業が使用者の企業に常駐する形で、業務についての指示を受けながら仕事をしている場合などが該当します。それ以外にも偽装請負に該当してしまうケースが存在しますので注意しましょう。代表的な形としては以下が挙げられます。
- 代表型: 発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、勤怠・勤務時間の管理を行ったりするケース。
- 形式だけ責任型: 現場に形式的な責任者しか置かれていないケース。その責任者が使用者の意志を請負の作業者に伝えているだけで、実態として発注者が指示を出しているのと同じ状況。
- 使用者不明型: 委託対象の業務が幾重にも再委託されているケース。
- 一人請負型: 実態として、A社からB社で働くように労働者を斡旋するが、B社はその労働者と労働契約は結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせるケース。
おわりに
業務委託の概要についてご理解いただけましたでしょうか。契約形態などの注意点を抑えれえば有効に活用できるリソースの一つとなります。新規にメンバーを雇用するよりも早く、手軽に取り組める手段となるので、ぜひ活用してみてください。