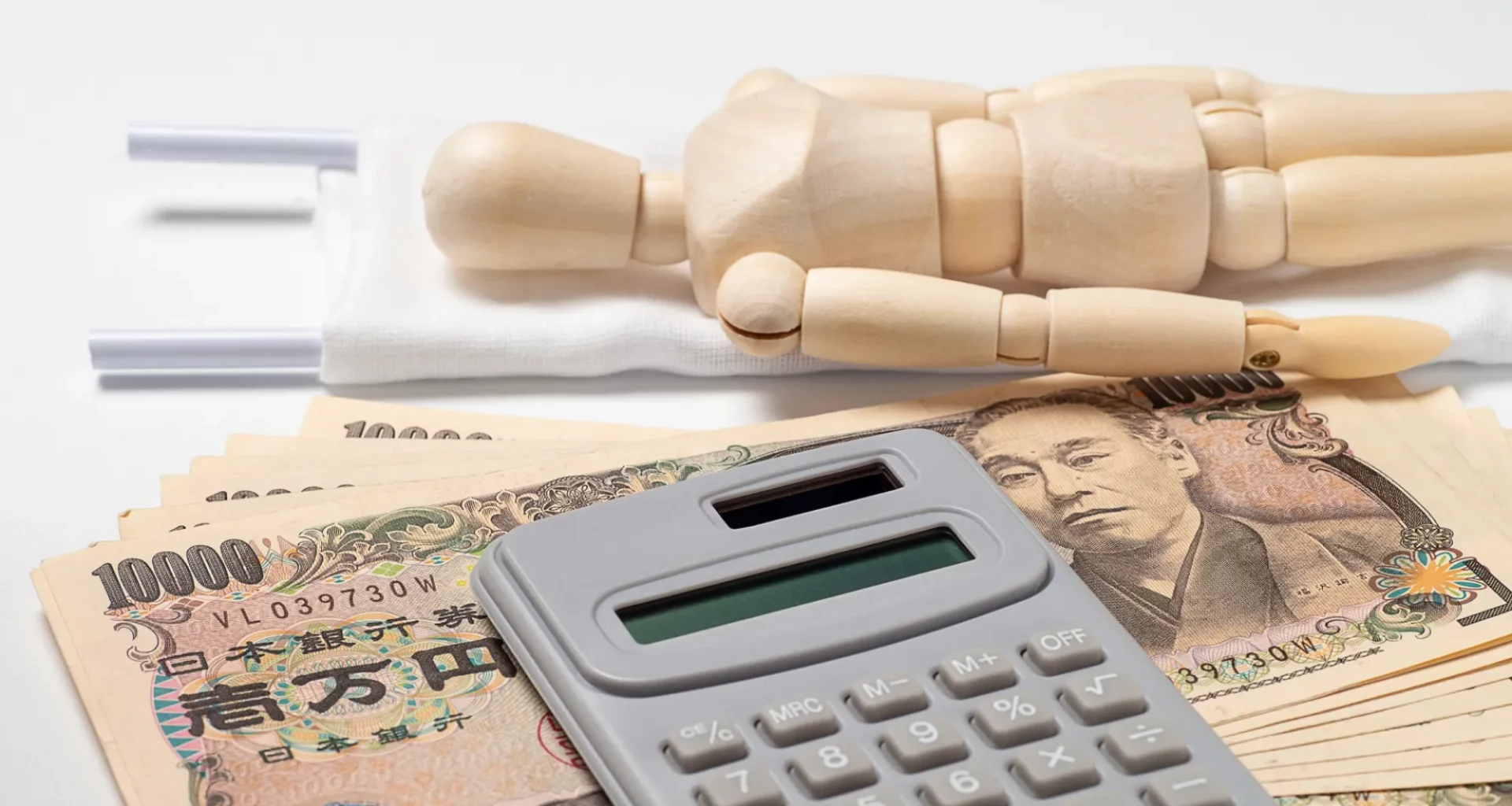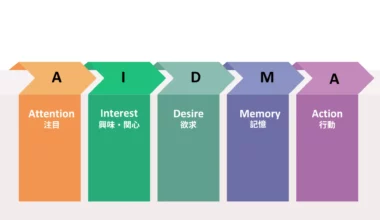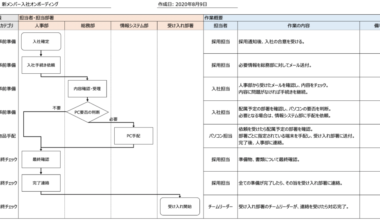サンクコスト(埋没費用)とは、すでに投下している取り戻せない費用のことです。回収不可能な過去の投資を「もったいない」と感じてしまう心理は、企業の重要な意思決定に影響を及ぼす可能性があります。
この記事では「サンクコスト効果」を取り上げ、その意味や具体例、回避するための対策についてわかりやすく解説します。
サンクコスト効果とは
サンクコストとは「埋没費用」のことで、事業を撤退しても回収が見込めない費用を指します。すでに資金や労力を投下しており、その後方向性を変えたとしても取り戻すことができなくなってしまったコストを意味します。
そして、これまでに費やしてきた資金や労力を惜しむあまり、合理的とは言い難い判断をしてしまうことを「サンクコスト効果」といいます。サンクコスト効果が働くと、その後の意思決定に影響が及びやすく、事業活動の停止や倒産といった企業にとって最悪の事態に陥ることもあり得ます。企業としてはサンクコスト効果を正しく理解し、これを回避するための対策を考えておく必要があるでしょう。
コンコルド効果との違い
サンクコスト効果と同義の言葉に「コンコルド効果」があります。他にも「コンコルドの誤り」や「コンコルドの誤謬」と呼ばれることがありますが、どれもサンクコスト効果と同じ意味合いを持つ言葉と捉えて差し支えありません。
コンコルド効果という名称は、イギリスとフランスが共同開発した超音波旅客機コンコルドの事例に由来します。開発途中から採算が取れないことがわかっていたにもかかわらず、投資したコストを惜しむゆえに開発を継続し、結果的に開発会社は倒産せざるを得なくなりました。この事例から、これまでに費やした資金や労力をもったいないと感じ、もはや引くに引けなくなっている現象を「コンコルド効果」と呼ぶようになったのです。
サンクコスト効果の具体例
サンクコスト効果は日常のさまざまなシーンで起こり得る心理現象です。
ここではサンクコスト効果が働く場面の具体例を紹介します。
日常生活で働くサンクコスト効果
日常生活におけるサンクコスト効果の具体例を紹介します。
読書
サンクコスト効果の身近な例が「読書」です。例えば書店で購入した本が期待外れだったにもかかわらず、気が向かないまま最後まで読み続けようとする行為はサンクコスト効果が働いているといえます。せっかくお金を払って購入したのだから、最後まで読まないのはもったいないと感じてしまい、自分にとってつまらない本に時間と労力を使っているからです。
恋愛
サンクコスト効果は恋愛をしているときにも起こりやすい心理現象です。相手のために多くの時間や労力、お金を費やしてきた場合、脈のない相手であっても諦められずに執着してしまうことがあります。また、これだけ尽くしているのだから自分と相手の関係は特別なものに違いないと思い込み、未来のない相手でも離れることができなくなってしまいます。
ギャンブル
ギャンブルもサンクコスト効果が働きやすい代表的な事例の一つです。基本的には負けが先行するものであると多くの人が知っていますが、こんなにお金を投入してきたのに今さらやめられない、投入した金額を取り戻さなければならないと、やめ時を見失って追加投入してしまいがちです。過去に儲けを出した成功体験があれば「次こそは当たるかもしれない」という淡い期待も抱いてしまうでしょう。
ビジネスシーンで働くサンクコスト効果
ビジネスシーンにおけるサンクコスト効果の具体例を紹介します。
新規事業
新規事業の立ち上げには多くのコストを費やす分、何が何でも成功させたい、投資分を回収しなければならないという気持ちが生まれやすくなります。しかし、新規事業が必ずしも成功するとは限らず、時には撤退の判断を余儀なくされることもあるでしょう。このときサンクコスト効果が働いていると、事業の中断や縮小、撤退などの判断が遅れ、赤字ばかりが膨らんでしまうおそれがあります。
マーケティング
マーケティングにおいては顧客のサンクコスト効果を利用している施策が多々あります。例えばサービスの利用に入会費や年会費、会員ランクを設定することで「今やめるのはもったいない」というサンクコスト効果が働きます。通販サイトなどでよく見られる「○○円以上の購入で送料無料」とするサービスも、顧客に「特典を受けなければもったいない」という気持ちにさせ、さらなる購入を促す効果があります。
サンクコスト効果が働く心理背景
サンクコスト効果が生じる心理背景には以下のようなものがあります。
損失回避
得をするよりも損失を避けることを重視する心理傾向を「損失回避」といいます。何を選択するかによって損得が分かれるような状況がある場合、人は「利益を得ること」よりも「損失を被ること」に敏感になるといわれています。意思決定をする際には「過去に投じたコスト」ばかりを気にしてしまい、これまでの労力を無駄にしたくない、損をしたくないという気持ちが働きやすくなります。
楽観主義
人は「損をしたくない」と考える一方で、自分が成功することに対して自信を持っている向きがあります。失敗する確率を過小評価し、これだけコストをかけたのだから成功するだろう、今は多少赤字でもこのまま継続すれば収益化できるだろうと考えてしまうのです。利益を出せる明確な根拠もなく将来を楽観視すると、合理的な判断をするべきタイミングを逃してしまうおそれがあります。
自己責任
コスト投入の判断を自分が下した場合、その責任を感じて事業やプロジェクトを止められなくなることがあります。自分の責任で物事を進めていると、十分な成果を得られていない状況で中断や撤退の判断を下すのは難しいと考える人も少なくありません。同時に、他人から「せっかく費やしたコストを無駄にしている」と思われたくないという気持ちも働き、まずます正しい判断ができなくなってしまいます。
サンクコスト効果を回避するための対策
程度の差こそあれ、サンクコスト効果が働くと合理的な判断が遅れてしまい、場合によっては企業の致命傷となるような多大な損失を被るおそれがあります。サンクコスト効果を回避し、合理的な判断を下すにはどのような対策が必要となるのでしょうか。
サンクコスト効果を理解する
サンクコスト効果を回避するにはまず「サンクコスト効果を知る」ことが重要です。これまでに費やしたコストを「もったいない」と感じる心理傾向は日常の至る場面で起こり得ること、しかしそれによって正しい判断ができなくなったり意思決定のタイミングを逃したりするリスクがあるということを理解します。
自分自身に働いているサンクコスト効果を自覚し、合理的な判断を下すためには過去にとらわれずに冷静かつ客観的に物事を見るべきだと心得ましょう。
ゼロベース思考で考える
ゼロベース思考とは、常識や慣習にとらわれずゼロの状態から物事を思考することです。サンクコスト効果を防ぐためには、サンクコストをなかったもの(=ゼロ)と仮定して物事を考えることが大切です。
事業やプロジェクトの継続・撤退の判断を下すときは、もう取り戻すことのできないサンクコストに固執せず、客観的なデータに基づく現状分析や将来予測を根拠とするのが望ましいでしょう。問題が複雑化して解決への道筋が見えなくなってきたときも、既存の枠組みを外してゼロベースで考えることで、これまで思いつかなかった斬新なアイデアが生まれることもあります。
判断基準を設定する
過去に多くのコストを費やしてきた場合、今は成果が出ていなくてもこのまま投資を続ければいつか芽が出るだろうと期待してしまうケースは少なくありません。このような心理傾向が起こり得ることを理解し、合理的な判断を下すための判断基準を前もって設定しておくことをおすすめします。
設定した基準を超える前に判断を下すことで損失を最小限に抑えられます。主観的な判断にならないよう第三者からの意見も取り入れながら、あらかじめ投資の上限や撤退のラインを明確にしておきましょう。
ビジネスでサンクコスト効果を活用する方法
サンクコスト効果は合理的な判断を妨げるおそれがあり、新しい事業やプロジェクトを進める際には注意すべき心理傾向といえます。しかし、マーケティング領域では顧客のサンクコスト効果をうまく活用し、商品やサービスの売上アップにつなげることができます。
サンクコスト効果を利用した施策には以下のようなものがあります。
- 入会金・年会費
- 会員ランク
- サブスクリプションサービス
- 無料お試し期間
- 付録付き月刊誌
- 来店者へのクーポンの配布
- ○○円以上の購入で受けられる特典
「せっかくお金を払っているのだから」「わざわざお店まで足を運んだのだから」と、かけたお金や労力に対する見返りを期待する気持ちは誰しも持っているでしょう。この心理を利用した施策を講じることで、顧客単価の向上や顧客離れの防止につなげられます。
また、商品の購入金額に応じてランクが上がる会員制度や、毎号の付録を集めて作品を完成させる付録付き月刊誌などは、途中でやめてしまうとこれまで費やしてきたコストがもったいないという気持ちにさせ、継続を促すことができます。
おわりに
サンクコスト効果とは、過去に費やしてきた回収不可能なコストを「もったいない」と感じ、合理的な判断ができなくなる現象をいいます。サンクコストの存在はその後の意思決定に影響を与えることがあり、企業にとって大きな損失につながってしまうおそれがあります。
この心理傾向を回避するには、サンクコスト効果が働きやすい状況や心理背景を理解し、重要な意思決定を行う際に過去のコストを考慮しないことが大切です。しかし、サンクコスト効果は無意識のうちに働くものでもあるため、あらかじめ投資金額の上限や事業撤退のラインを設定しておくのが望ましいでしょう。サンクコスト効果の存在を自覚したうえで、合理的判断を下すための対策を講じておくことが重要です。