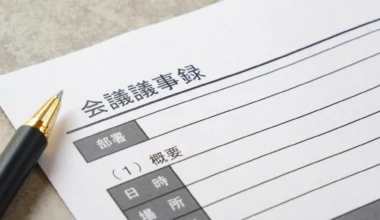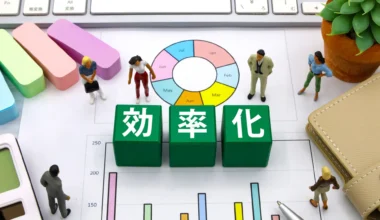部署異動や転勤、退職などで業務の担当者が変わるとき、現在の担当である前任者は次の人へ業務を引き継ぐために「引継ぎ資料」を作成します。この記事では、引継ぎ資料の作成手順とともに、資料が必要な理由や作り方のポイントを解説します。
引継ぎ資料とは
引継ぎ資料とは、業務の担当者が変わる際に、業務内容を後任者へ引き継ぐために使用する書類全般のことです。後任者へ伝えるべき事柄をわかりやすくまとめた書類を作成し、丁寧な引継ぎを行うことで、次に業務を担当する人が滞りなく業務を遂行できる状態にします。
引継ぎが必要になる場面
引継ぎ資料が求められるのは「引継ぎが発生する場面」です。例えば以下のようなシーンで引継ぎが発生し、業務内容を伝達するために引継ぎ資料が必要となります。
- 前任者の部署異動
- 前任者の転勤
- 前任者の退職・離職
- 前任者から後任者への業務譲渡
部署異動や転勤、退職などにより、その業務の担当者が不在となる状況で引継ぎの必要性が生じます。また、これまで先輩が行っていた業務を後輩へ任せる場合など、前任者が同じ部署に留まっていても引継ぎが必要となることがあります。
業務マニュアルとの違い
業務マニュアルも引継ぎの際に必要となる書類の一つです。引継ぎ資料も業務マニュアルも業務内容について記載されていますが、業務マニュアルではその業務の概要や手順などが標準的にまとめられています。一方、引継ぎ資料には個人的な内容も含み、業務遂行に関わる社内外の関係者や現時点で未処理となっている事項なども記載します。
業務マニュアルの作り方やコツについては以下の記事で詳しく解説しています。本記事とあわせて参考にしてみてください。
マニュアル作成のコツ7選|失敗しない作り方と運用時のポイント
引継ぎ資料が必要な理由
引継ぎ資料が必要な理由として以下の点が挙げられます。
スムーズな引継ぎを行うため
担当者の変更によって引継ぎが発生した際、引継ぎ資料が用意されているとスムーズかつスピーディーな引継ぎを行うことができます。その部署の状況や業務内容、後任者の知識レベルにもよりますが、業務の引継ぎに時間をかけられないことも多いため、引継ぎ時には伝えるべき内容を漏れなくまとめた引継ぎ資料が重宝されます。
また、引継ぎ資料があれば後から何度も見返すことができ、後任者の不安軽減にもつながります。引継ぎは口頭だけで済ませるのではなく、後任者が必要なタイミングでいつでも確認できるように文書化しておくことが大切です。
業務の属人化を防ぐため
属人化とは「担当者以外が業務の内容を把握できていない状態」を指します。高い専門性が求められる業務や立ち上げ期にある業務など、一部の業務では属人化の状態がメリットとなり得ます。しかし、手順が決まっている定型業務や安定した品質が重視される業務については、担当者しかその業務を知らないという状態を防がなければなりません。この点、引継ぎ資料があれば、前任者だけが把握している情報を後任者へ伝えられ、業務の属人化を防止できます。
仕事の品質を維持するため
企業として避けなければならないのが、担当者の変更で生じる仕事の品質への影響です。担当者が変わったことで、仕事の品質が落ちてしまう、安定した品質を維持できなくなるという事態が起こらないようにしなければなりません。業務内容や手順だけでなく、未処理事項やトラブル時の対処法などもまとめた引継ぎ資料を用意し、後任者に対してしっかりと引継ぎを行っておくと、担当者が変わっても品質が落ちることはありません。仕事の品質は社内外からの信頼にも影響するため、限られた時間でも漏れなく丁寧に引継ぎを行うことが重要です。
引継ぎ資料を用意するメリット
引継ぎ資料の作成には時間を費やしますが、前任者の責任としてできる限り丁寧に、具体的かつわかりやすい資料を用意することが求められます。そして、このような引継ぎ資料には以下のような効果があります。
- 後任者の負担を軽減できる
- 抜け漏れのない正確な引継ぎが行える
- 業務効率化と生産性の向上につながる
- 顧客からの信頼を維持できる
口頭だけの引継ぎでは「言った・言わない」の問題が生じたり、伝え漏れがあっても気づかなかったりと、正確な引継ぎを行えない可能性があります。引継ぎ資料を用意し、それをもとに引継ぎを行うことで、後任者の負担軽減と不安の解消につながります。
また、引継ぎ資料を作る際は業務の棚卸しを行い、業務内容や手順をあらためて整理することになります。このとき、無駄な作業や手順を省いて業務を最適化できれば、今までよりも業務効率が上がり、仕事の生産性向上につながるでしょう。
引継ぎ資料の作成手順
引継ぎ資料の作成ステップを紹介します。
STEP1:引継ぎのスケジュールを立てる
引継ぎ資料を作り始める前に、まずは引継ぎのスケジュールを決めておきます。
後任者に丁寧に引継ぎを行うためには、なるべく余裕を持ったスケジュールを設定する必要があります。前任者が転勤や退職などで職場から離れる場合は、少なくとも最終出社日の3日前までには引継ぎを終わらせておくのが望ましいでしょう。多くは通常業務と並行しながらの引継ぎとなるため、通常業務にかかる時間と引継ぎにあてられる時間を計算しながら、無理のないスケジュールを立てておくことが大切です。
STEP2:引継ぎを行う業務内容を洗い出す
次に引継ぎ対象となる業務を洗い出し、一つずつリストアップしていきます。
業務の中には日常的に発生する業務もあれば、月次や年次などで時々発生する業務もあります。このようなたまにしか発生しない業務も漏れなくリストアップし、後任者が担当する業務をすべて網羅できているか確認しましょう。あわせて、引継ぎ資料に記載する項目を整理し、項目ごとに必要な情報をまとめておきます。
【引継ぎ資料に記載する項目の一例】
- 業務の目的と流れ
- 業務の関係者
- 業務の作業手順
- 過去のトラブル例と対処法
- 必要書類の保管場所
- 現時点での未処理事項
STEP3:引継ぎ資料を作成する
リストアップした業務内容や関連する情報を引継ぎ資料に落とし込んでいきます。
引継ぎ資料を作成する際は、誰が読んでもわかるようにまとめることが大切です。業務によっては専門用語を用いて説明することもありますが、その場合は注釈を付けるなどしてその用語を知らない人が読んでもわかるようにしておきます。特に複数の部署が関わる業務の場合は、後任者以外の他部署の人が読むことも想定しながら作成するとよいでしょう。
また、標準的な業務マニュアルとは異なり、引継ぎ資料には個人的な情報も記載します。業務の関係者や関係性、未処理事項、自分だけが把握しているノウハウなど、後任者が知っておくと役立つ情報もまとめておきましょう。
STEP4:後任者へ引継ぎを行う
作成した引継ぎ資料をもとに、後任者へ引継ぎを行います。
引継ぎ資料を読んで理解したつもりでも、実際に作業をしてみるとわからない箇所が出てきたり、自分の理解が誤っていたりすることがあります。前任者としても引継ぎ資料を渡して終わりではなく、実作業を通してレクチャーし、後任者が滞りなく業務を行えるか確認しましょう。また、引継ぎ資料に足りない情報があれば追記する、わかりにくい箇所があれば改善するなどして、引継ぎ資料の内容をアップデートしていくことも大切です。
引継ぎ資料を作成するときのポイント
引継ぎ資料を作成するときに意識したいポイントを以下にまとめました。
後任者の知識レベルに合わせる
引継ぎ資料は後任者の知識レベルに合わせて作成します。その業務を熟知している前任者としては「これは説明しなくてもわかるだろう」と判断しがちですが、後任者の業務知識が不足している場合には伝わらない可能性があります。後任者の知識レベルがわからないときは「初めてその業務を行う人」を想定し、知識がなくても引継ぎ資料を読めばスムーズに業務を進行できる状態にするのが理想です。
必要な情報が漏れなく記載できているか確認する
引継ぎ資料には後任者が知っておくべき情報を漏れなく記載します。
情報の抜け漏れを防ぐためには、MECE(ミーシー)と呼ばれる概念が役立ちます。MECEとは「モレなく、ダブりなく」を意味する用語で、以下4つの英単語の頭文字をとっています。
- Mutually(互いに)
- Exclusive(重複せず)
- Collectively(全体に)
- Exhaustive(漏れがない)
MECEは論理的思考力(ロジカルシンキング)の基本であり、あらゆるビジネスシーンで活用できる概念です。情報を落とし込むときには「モレなく、ダブりなく」を意識し、精度の高い引継ぎ資料を作成しましょう。
第三者からフィードバックを受ける
引継ぎ資料を作成したら、後任者に渡す前に社内の第三者に確認してもらい、フィードバックを受けることをおすすめします。第三者の視点から引継ぎ資料を確認すると、情報が少なくてわかりづらい、誤解を招く表現がある、業務のつながりが把握できないなど、前任者が気づかなかった新たな課題が見つかることもあります。指摘を受けた箇所はすぐに改善し、アップデートしてから後任者に渡しましょう。
おわりに
引継ぎ資料とは、業務を他の人へ引き継ぐときに必要となる書類全般のことです。引継ぎ資料がなければ、後任者はスムーズに仕事を進めることができず、仕事の品質が落ちてしまうおそれがあります。後任者に負担がかからないよう、前任者は責任を持って担当業務を整理し、自分が不在になる前に引継ぎを完了させておくことが求められます。
引継ぎ資料を作成する際は、あらかじめ引継ぎのスケジュールを決め、引継ぎ対象の業務をリストアップしておくとスムーズです。資料作りやレクチャーは通常業務と並行して行うことになるため、前任者としても負担がかかりますが、次の担当者が困らないように丁寧な引継ぎを心がける必要があります。今回紹介した「引継ぎ資料を作成するときのポイント」も参考にしながら、精度の高い資料作りに取り組んでみてください。