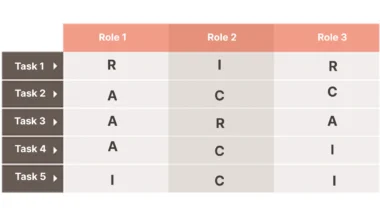アクティブリスニング(Active Listening)とは、相手の言葉に共感と関心を持って積極的に耳を傾けるコミュニケーション技法です。
話し手の言葉に耳を傾け、相手の意見や本音を引き出す傾聴力は、上司や管理職が身につけておくべき必須のスキルといえます。
この記事ではアクティブリスニングの基礎知識とともに、期待できる効果や具体的な手法についてわかりやすく解説します。
アクティブリスニングとは
アクティブリスニング(Active Listening)とは、相手の言葉に共感と関心を持って積極的に耳を傾けるコミュニケーション技法のことです。提唱したのはアメリカの臨床心理学者であるカール・ロジャーズ氏で、日本語では「積極的傾聴」と訳されています。
ビジネスシーンで注目される理由
アクティブリスニングはカウンセリングで用いられてきた技法ですが、近年ビジネスシーンにおいても活用されています。人材育成におけるマネジメントや良好な人間関係の構築など、さまざまなシーンでアクティブリスニングを有効に活用できるからです。
特に上司や管理職など職場内で上の立場にある人が積極的傾聴を用いることで、部下は「信頼されている」「理解されている」と感じ、上司と部下との間に信頼関係が築かれます。適切な質問により相手が自ら考えるように働きかけ、部下の自発的な成長を促すこともできます。
傾聴との違い
アクティブリスニングと傾聴は同じ意味合いで使われることが多く、どちらも相手の話に積極的に耳を傾けるコミュニケーション技法です。ただし、傾聴には「積極的傾聴」の他にも「受動的傾聴」や「反映的傾聴」と呼ばれる技法があります。
アクティブリスニングは傾聴の一種ですが、話を聴きながら適切な質問を挟んで相手の思考を促していきます。ただ受動的に話を聴くのではなく、より相手の話に踏み込んでいく能動的な技法といえるでしょう。
アクティブリスニングの3原則
アクティブリスニングの提唱者であるカール・ロジャーズ氏は、自らのカウンセリング事例を分析し「聴く側の3要素」を導き出しました。
- 共感的理解(empathy, empathic understanding)
- 無条件の肯定的関心(unconditional positive regard)
- 自己一致(congruence)
これらは有効なカウンセリングに共通する要素として挙げられたものです。アクティブリスニングを実践する際はロジャーズの3原則を心がけるとよいでしょう。
共感的理解
共感的理解とは、相手の立場に立って共感を示しながら傾聴することです。ただ話を聴くだけでなく、相手の言葉を繰り返したり相づちを打ったりして、話の内容を理解している・共感していることを表現します。こうすることで話し手は「私の気持ちをわかってくれている」と感じ、安心して自分の思いを話せるようになります。
無条件の肯定的関心
無条件の肯定的関心とは、相手の話を否定せずに肯定的な関心を持って傾聴することです。話の内容に関して善悪の評価を入れず、まずは「なぜそう考えるようになったのか」と話の背景に関心を寄せることがポイントです。初めから相手の話を否定するような言動をとってしまうと、相手は萎縮してそれ以上話せなくなってしまいます。
自己一致
自己一致とは、聞き手が「感じていること」と相手に対する「言葉や態度」が一致していることをいいます。自己一致に基づく傾聴は、相手だけでなく自分に対しても真摯な姿勢で聴くことを意味します。相手の話にわかりにくい部分があればそのままにせず、「それはこういう意味で合っていますか」と確認して真意を確かめます。理解できていないにもかかわらず「そうですね」「わかります」と共感する態度をとるのは望ましくありません。
アクティブリスニングで期待できる効果
アクティブリスニングを取り入れることで以下のような効果が期待できます。
信頼関係の構築
アクティブリスニングにはコミュニケーションの活性化や良好な人間関係の構築につなげる効果があります。上司が部下の話を真摯な姿勢で聴くことで、部下は安心して自分の気持ちや思いを伝えられるようになり、両者の間に信頼関係が築かれます。部下は上司に対して本音を伝えづらいからこそ、上司が積極的に部下の話に耳を傾ける姿勢を持つことが大切です。上司と部下だけでなく、同僚同士のやりとりでもアクティブリスニングを有効に活用することで、円滑なコミュニケーションや協力体制がとれるようになります。
ハラスメントの防止
職場内のハラスメント防止策としてもアクティブリスニングを活用できます。社内の風通しが良く、上司と部下との間に信頼関係が構築されている職場ではハラスメントが起こりにくいからです。相手の話に関心を持ち、理解や共感を示しながら聴くことで、自分の意見やアイデアを安心して表現できる「心理的安全性」の高い組織をつくることができます。ハラスメントの起こらない組織では社員のパフォーマンスが上がりやすく、仕事の効率アップや業績向上につながることが期待できます。
問題解決能力の向上
問題解決能力とは、発生した問題の原因を分析し、対応可能な最善の解決策を導き出すスキルのことです。アクティブリスニングでは適切な質問を投げかけ、相手が自ら問題の原因や解決の糸口を見つけられるようにサポートします。聞き手が一方的に助言したり解決策を提示したりするのではなく、「そのときどう思いましたか」「どうすればよかったと思いますか」などと質問し、話し手に考えさせることが重要です。
アクティブリスニングを実践する方法
アクティブリスニングを実践する方法として、言葉を用いる「バーバルコミュニケーション」と言葉以外で行う「ノンバーバルコミュニケーション」があります。それぞれどのような手法があるのか、言語・非言語の具体的なコミュニケーション方法を紹介します。
バーバルコミュニケーション
バーバルコミュニケーションとは、会話や文字など言葉を使って行う言語的なコミュニケーションのことです。アクティブリスニングに役立つ手法として以下が挙げられます。
■オープンクエスチョン
オープンクエスチョンとは、相手の答えが制限されない質問のことです。「はい」か「いいえ」で答えられない質問と考えるとイメージしやすいでしょう。アクティブリスニングでは相手の本音を引き出したり自ら考えることを促したりするため、二者択一で簡単に答えられる質問よりも、相手の意見や気持ちを自由に表現してもらえる質問のほうが向いています。
■パラフレーズ
パラフレーズとは、相手が話した内容を自分の言葉で言い換えることをいいます。相手の言葉を繰り返す「パロット」(オウム返し)からさらに一歩進み、「つまりこういうことですか」「こういう理解で合っていますか」と聞き手の言葉で再表現します。これにより、相手は「自分の話をしっかり聞いてくれている」「積極的に理解しようとしてくれている」という安心感を感じます。話の内容を互いに整理するうえでも有効な手法です。
ノンバーバルコミュニケーション
ノンバーバルコミュニケーションとは、目線や表情、身振り手振りなど言葉以外の要素を用いる非言語的なコミュニケーションのことです。アクティブリスニングを実践する際は以下の要素を意識するとよいでしょう。
■姿勢
アクティブリスニングでは、相手のほうに体を向けて聴く姿勢をつくり、相手の言葉に真剣に耳を傾けます。「聞いてやっている」というような横柄な態度、例えば腕や脚を組んだり反り返ったりすることは避けるべきでしょう。相手の本音を引き出すには、緊張せずにリラックスして話せる雰囲気をつくることが大切です。
■目線・表情
話を聴くときは相手と目線を合わせ、相手の感情に合わせた表情をつくりましょう。ただし、目線を合わせすぎたり大げさに表情をつくったりすると、かえって話しにくくなってしまいます。理解や共感を示すことは重要ですが、相手が話しやすいかどうかを常に気にかけ、目線や表情は適度に合わせることを意識しましょう。
■声のトーン
話す言葉の内容以上に、声の大きさや抑揚、スピードなども意識すべきポイントです。聞き手のトーンが低いと、相手は「怒らせているのではないか」「機嫌が悪いのではないか」と感じ、安心して話すことができなくなってしまいます。話を聴くときは適度に相づちを入れながら、相手の表情や話の内容に合わせて声のトーンを調節するようにしましょう。
アクティブリスニングの注意点
アクティブリスニングでは、話し手が自ら考えて問題の本質を理解できるように働きかけます。話を聴いた上司が問題の原因や解決策を提示するなど、聞き手が話の内容を結論づけるべきではないことに注意が必要です。
話を聴いていくなかで「こうすればよいのではないか」と意見を持つことは当然ありますが、それを主張してしまうと相手は自分で考えることを放棄してしまうかもしれません。聞き手の役割は「話を聴く」ことであり、話の内容に応じたリアクションをとりながら相手の考えを引き出していきます。相手の話に耳を傾け、適切な質問をして相手に「考えること」を促し、自ら解決策を見つけられるようにサポートすることが大切です。
おわりに
アクティブリスニング(積極的傾聴)とは、理解や共感を示しながら相手の言葉に積極的に耳を傾けるコミュニケーション技法です。聞き手は自我を出さず「聴くこと」に専念し、適切な質問を通じて相手に考えさせ、自ら問題の本質や解決策を見出せるように支援します。
アクティブリスニングを取り入れることで、職場における信頼関係の構築やハラスメントの防止、問題解決能力の向上といった効果が期待できます。部下とのコミュニケーションや職場内の人間関係に課題を感じている場合は、上司が率先してアクティブリスニングを実践することをおすすめします。