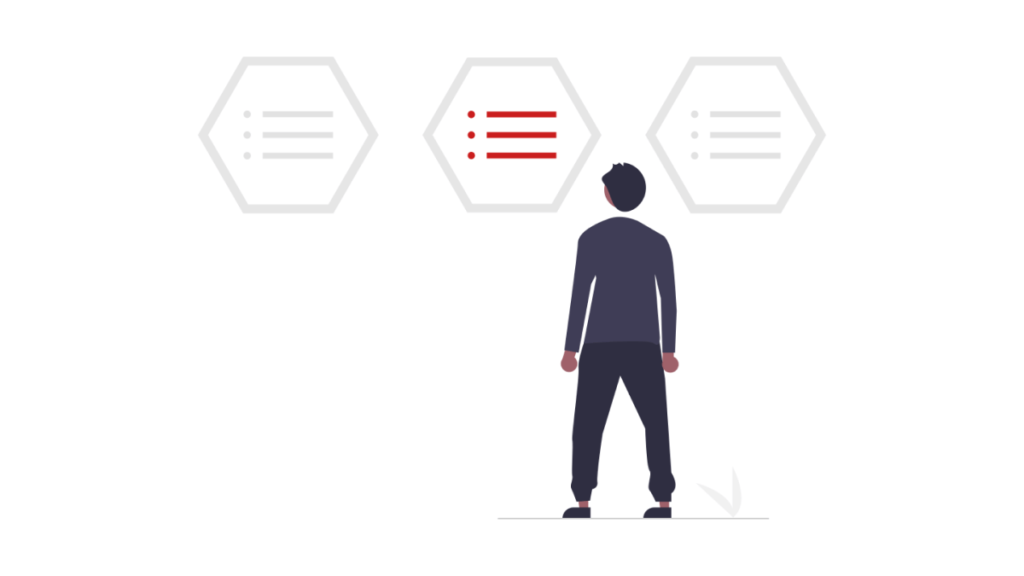本記事では、BPM(ビジネスプロセスマネジメント)について、弊社や弊社がサポートしていた企業様の事例をご紹介しています。実際の取り組みに関する詳細を記載していますので、自社で取り組むかを判断される際にぜひ参考にしてください。
おさらい|BPMとは
BPMはBusiness Process Management(ビジネスプロセスマネジメント)の略称で、ざっくりまとめるとビジネスプロセスの管理によって、定型業務・定常業務の継続的な改善を目指す活動のことを指します。特に以下の2点が特徴的な業務改善方法です。
- 業務をプロセス単位で管理すること
- 継続的な取り組みによる改善を前提としていること
また、BPMの基本概要について記載している記事もありますので、まずは概要を知りたいという方は以下の記事を確認してみてください。
BPMの事例5つ
今回は、弊社で運用している業務、弊社が過去にサポートしてきた業務の中からBPMの事例を5つご紹介します。業種や業務内容、規模が異なるフローを選んでいますので、自社に近い業務フローがないか、確認しながら読んでみてください。
また、BPMは以下の5つのステップで進行していきます。この記事の中でご紹介する事例についても以下の流れに沿って実施されています。具体的なBPMの流れについて解説している記事もありますので、参考にしてください。
1: 入社対応業務
中途入社が発生した際の対応フローです。ほとんどの企業で同様の業務が発生するかと思いますが、弊社がサポートした企業様は全国に支店があり、全支店で毎月発生する中途入社の対応を本部が請け負っていたため、本部・支店・入社者間のやりとりに課題を感じていました。
業務内容
基本的には、次月入社が確定したメンバーの対応を当月中に行います。中途入社が確定したら、入社予定日までに以下の準備を全メンバー分行っておく必要がありました。
- 社員番号の割り振りと通知
- 雇用契約書の作成と送付
- 社内システムへのアカウント招待
- 入社関連書類の回収(身分証明書や住民票など)
- 各種保険の手続き(健康保険や雇用保険の加入、住民税の徴収手続きなど)
特に書類の提出については、各支店で本人から原本を回収後、現場から本部へ報告、本部で内容を確認し不備や抜け漏れがあれば電話で修正を依頼するなど、遠隔地ならではのコストが発生していました。
また、各支店のメンバーは通常の現場作業と並行して必要書類の回収を行う必要があったため、忙しさから頻繁に対応漏れが発生していました。
BPMの取り組み内容
現場のメンバーとのやり取りの煩雑さを解決するためBPMに取り組み始めました。業務一覧表は存在していましたが手順やフロー、進捗状況は可視化されていなかったため、はじめに業務内容をexcelの表にまとめてからツール導入を行いました。
また、支店数が多くいきなり全ての業務を移行することはリスクが大きかったため、はじめは2支店のみに絞ってツール導入を行い、徐々に利用支店数を増やしていくよう取り組みました。
取り組みの結果
ツール上で業務状況を可視化できるようになったことで、現場メンバーの作業中の抜け漏れや遅れが削減されました。また、従来は電話で進捗を確認する必要がありましたが、ツールを見れば進捗状況をリアルタイムに把握できることから、連絡の手間も省くことが出来ました。
今後は、入社対応だけでなくその他の総務業務や支店長のタスク管理でもBPMを活用していく予定です。
2: システム運用フロー
続いて、サーバーメンテナンス業務を受託している企業様の事例です。規模も大きく、もともと業務管理に力を入れていたためオペレーションは整備されていましたが、更なる業務効率化のためにBPMに着手し始めました。
業務内容
管理しているサーバーでエラーが発生した際に作業者に通知し、作業者が修正対応を行います。ミスが発生すると顧客の業務に支障をきたすクリティカルな業務です。
画像の流れはシンプルですが、実際には発生したエラーの種類によって対応が何十種類にも分岐します。したがって作業者は該当するエラーの対応を何百ページとあるマニュアルから探し出す必要がありました。また、操作方法のマニュアルとは別に作業結果を管理するためのチェックリストも存在しており、マニュアル・チェックリストを同時に開いて作業・記録を行う手間も生じていました。
BPMの取り組み内容
日頃利用しているマニュアル、チェックリスト、進捗管理を1つのツールにまとめることを目的として取り組みを開始しました。関係者が多いこと、24時間稼働であること、既存の取り組み方法が既に浸透していたことなどから取り組みを以下のように段階を分けて実施しました。
- 導入したいツールの理解
- 取り組み内容: ツールを触り、まずは使用感を確認。
- 関わる人数: 導入担当3名
- 業務効率化の可否を確認
- 取り組み内容: ツールの費用対効果を確認するため、少人数で試験的に運用。
- 関わる人数: 現場メンバー5名(全体のうちの1/3)
- 大人数での運用可否を確認
- 取り組み内容: 最終的に15名程度での利用を想定していたため、利用者を増やし、利用範囲の拡大が可能かを確認。
- 関わる人数: 現場メンバー10名(全体のうちの2/3)
- 業務の全移行
- 取り組み内容: 既存の取り組み方法を停止し、新しい方法へ全員で移行。
- 関わる人数: 全員(15名)
実際には、4つの流れのほかにツールの選定、現場メンバーへのツールのインプットなどの細かな業務もいくつか行なっています。
取り組みの結果
現在は当初の想定通り、ひとつのBPMツールに業務に必要な情報をまとめ、BPMツールとアラートシステムを併用しながら対応しています。業務情報が整理されたことで作業のミスや抜け漏れを防げるようになり、また、業務の記録が残るため管理者の作業チェックのコストも削減することができました。基本的な定型業務はツール内で管理できることが分かったため、今後は条件分岐が必要な業務への拡大や、自動化を組み合わせた処理を想定しています。
3: 記事執筆フロー
こちらはメディアやブログを運営している企業様の、記事の執筆から公開までのフローです。制作担当者が記事を制作し、管理者が原稿をチェック、その後公開という流れで進行します。十名以下の小さなベンチャー企業だったこともあり業務情報が整えられておらず、対応が属人化していました。
業務内容
こちらの企業様では、記事の執筆作業を外部のライターに委託していました。個人で活動している複数名のライターに執筆を依頼していたため、作業内容のチェックや納品後の請求作業などのルーティン業務をライターの人数分実施する必要がありました。また、作業の進捗状況が可視化されていなかったため納期遅れが発生したり、オペレーション全体が統一されていなかったため新規に雇用したライターとのやりとりが煩雑になったりといった課題が発生していました。
請求書の管理は、『SmartDeal(スマートディール)』がおすすめです。
BPMの取り組み内容
定型的な業務であったことからBPMを検討し、手順と進捗状況を可視化するためにツールを導入しました。業務の流れがシンプルだったため箇条書き程度にタスクを洗い出してからツールに業務情報を登録しました。
また、作業者が頻繁に代わるため作業者はツールに含まず、管理者のみの利用としました。業務改善というとチーム全員の業務の変更が必要なように思われますが、一部の業務や管理方法を変えるだけでも十分に効率化を実現できます。
取り組みの結果
業務フローとタスク・進捗状況が明らかになったことで進捗確認のタイミングが明確になり、作業者の納期遅れを防げるようになりました。また、BPMに取り組む中で業務情報を整理することができたため、新規に依頼したライターに対する業務情報のインプットや日々のコミュニケーションにおいてもスムーズなやりとりが可能になりました。
4: 精算・請求業務
ある事務所での月次対応業務として、精算・請求管理にBPMを取り入れました。業務の一部をアウトソースしていたためアウトソース先の企業とのやりとりが必要であり、且つ、期限が厳密に決まっているため遅れが許されないという特徴がありました。
請求書の管理は、『SmartDeal(スマートディール)』がおすすめです。
業務内容
毎月決まった日時までに、当月に発生した費用を計算して精算書を作成します。同時にアウトソース先の情報提供も必要なため、アウトソース先の対応を待つ場面も多く、毎月期限に追われながらバタバタと作業していました。また、使用しているシステムが使いづらかったため対応が可能なスタッフが限られていたり、手順がまとめられていないためメンバーの入れ替えがあった場合にインプットができなかったりと、属人化にも課題を感じていました。
BPMの取り組み内容
将来的にはツールの導入を見据えつつ、まずは手順書の作成をゴールとして取り組み始めました。手順書の作成担当を1名決め、そのメンバーが他の作業者にヒアリングをしながら業務を整理、ある程度の情報が集まってきたら、マニュアルツールに清書をしました。通常業務と並行していたため、3~4ヶ月かけて実施しました。
ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。
取り組みの結果
最終的に、業務のフロー図、手順、担当者、期限などの業務に関わる情報をひとつの手順書にまとめあげました。手順が可視化されたことで本来一部のメンバーしか対応できなかった業務を複数名のメンバーで対応できるようになっただけでなく、一度作成した手順書を原本として複数回修正を繰り返し、さらに業務をコンパクトにすることに成功しました。今後は、可視化した業務の進捗状況を管理するためのツールの導入を予定しています。
5: 新規顧客のオンボーディング対応
こちらはスタートアップでの事例です。自社サービスのトライアル利用があった際に、トライアル時の対応の管理にBPMを利用しました。立ち上げたばかりだったためフローが固まっていませんでしたが、今後を見据えて業務を可視化しておくため、早めにBPMを取り入れました。
業務内容
自社サービスのサイト上のフォーム回答からトライアル利用の申込を受け取った後、以下のような対応を行っていました。
- トライアル利用者へのデモンストレーション(お打ち合わせ)の打診、日程調整
- お打ち合わせの実施
- トライアル環境の発行とお渡し
- ご状況確認のためのお打ち合わせ
- 継続利用であれば有料化の開始、そうでなければ停止対応
上記の画像では1つのみですが、サービスのトライアルにおいては複数の分岐が発生します。例えばトライアル期間中の利用状況によってご案内方法を変更したり、継続利用いただくものの予算取りの関係で有料化のタイミングがずれたりなどです。それらの対応内容が標準化されておらず、担当者ごとの判断でご案内を進めてしまっていました。
BPMの取り組み内容
BPMツールの利用を通して業務を改善していくことを決め、はじめからツールを導入しました。手順書やフロー図も存在しなかったため、ツールに情報登録していく中で業務を可視化し、プロセスを変更するごとにツール上の情報も書き換えながら運用しました。
取り組みの結果
複数の企業のトライアルが同時進行した際に、企業ごとの進捗状況を把握しやすくなり、その結果作業の抜け漏れを削減することができました。今後トライアル企業数の増加が見込まれるため、規模の小さいうちから管理方法を固めておくことで業務拡大に備えられたこともポイントとなりました。
また、そのツールを見れば全ての情報が分かるので、作業者としては“自分で記憶しておく必要がない”ことから心理的な負荷を下げられたことも大きなメリットでした。
BPMに利用できるツール
今回ご紹介したように、BPMの取り組みにはBPMに特化したツールを利用されるケースも多くあります。また、BPMを専門としているコンサルタントなどに依頼するよりも、ツールの導入を通して改善に取り組んだ方がコストパフォーマンスの面では優れているケースがあったり、気軽に取り組み始められたり、といったメリットもあります。BPMに特化したツールを紹介している記事もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
弊社で提供しているプロセスマネジメントツール「octpath」は、フロー形式でタスクや手順、作業記録の管理ができるサービスです。作業漏れのアラートやリマインドによるミスの未然防止や、自動条件分岐などの機能により、作業の管理コスト自体を削減できます。
また、UIがシンプルなためBPMに初めて取り組まれる方でも簡単に操作が可能です。詳細はサービスサイトを確認してみてください。
終わりに
BPMは取り組んだことがないとなかなかイメージが持ちづらくはありますが、実際の取り組みの内容は至ってシンプルです。また、今回取り上げた例からも分かるように、業種や業界、業務内容を問わず幅広く取り入れられる手法です。取り組んでいる企業様も徐々に増えてきていますので、ぜひ検討してみてください。