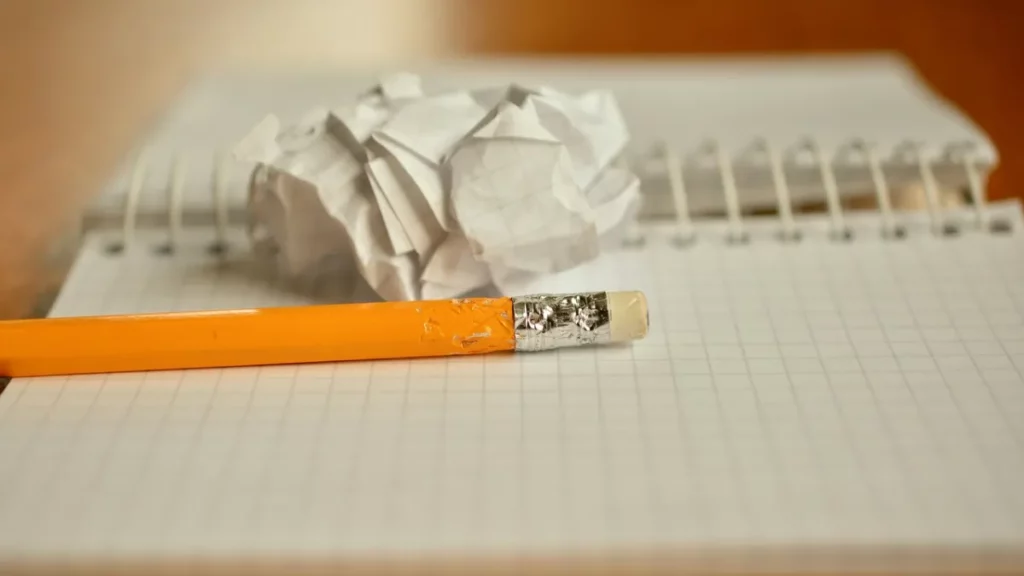ビジネスシーンで広く使われる「レギュレーション」。仕事の品質や公平性を確保するうえで欠かせないものであり、健全かつ公正な組織運営のためにはレギュレーションの遵守が必須となります。
この記事では「レギュレーション」を取り上げ、言葉の意味や使い方、効率的に管理する方法についてわかりやすく解説します。
レギュレーションとは
レギュレーションとは「規則」や「規制」を意味する言葉で、英語の「Regulation」に由来します。ビジネスシーンで広く使われており、自社のさまざまな取り決めを定めた「社内規程」や、就業に関するルールを定めた「就業規則」などを指します。
一般的にはさまざまな「守るべき決まりごと」を意味する言葉ですが、レギュレーションの意味や使い方は業界によって変わることがあります。レギュレーションと似た意味を持つ言葉も多いため、次項を参考にどのように使い分けるべきか押さえておくとよいでしょう。
レギュレーションと類似する言葉との違い
レギュレーションと類似する言葉に「ルール」や「コンプライアンス」があります。これらの言葉とレギュレーションにはどのような違いがあるのでしょうか。
ルールとの違い
ルールは「規則」を意味する言葉で、一見「レギュレーション」と同じ意味を持つ言葉のように思えます。しかし、言葉が持つ拘束力に違いがあり、レギュレーションは「必ず守らなければならない規則」である一方、ルールは「守るべき(守るのが望ましい)規則」といえます。
レギュレーションが指す「規則」は守らなければ法律違反となることもありますが、ルールが指す「規則」はそこまで強い意味を持たず、守れなかったとしても大きな問題となることは少ないでしょう。
コンプライアンスとの違い
コンプライアンスは「法令遵守」を意味する言葉で、企業・個人が社会の一員として法令やルールを守ることをいいます。遵守すべきは法令だけでなく、企業であれば自社の就業規則や社会倫理(社会から求められる倫理観)なども該当します。
レギュレーションは「規則そのもの」を指す言葉であるのに対し、コンプライアンスは「規則を守ること」を指す言葉です。また、コンプライアンスの対象は限定的であり、さまざまなシーンで使われるレギュレーションとはこの点でも違いがあります。
業界別|レギュレーションの使い方
レギュレーションの使い方は業界によって違いがあります。ここでは4つの異なる業界を例に「レギュレーション」がどのように使われているか紹介します。
IT・Web業界のレギュレーション
IT・Web業界で使われる「レギュレーション」には、広告の入稿規程、Webサイトの個人情報保護、データセキュリティなどがあります。例えばリスティング広告(検索連動型広告)では、媒体ごとに「文字数」「使用可能記号」「禁止事項」などのレギュレーションを設けています。
また、コンテンツ制作においても「メディアの目的」「トンマナ」「文字数・装飾のルール」などを統一するためにレギュレーションが使われています。事前にこれらのルールをまとめて共有することで、メンバー全員が同じ認識で取り組めるようになり、統一感のあるコンテンツを作ることができます。
医療業界のレギュレーション
医療業界で使われる「レギュレーション」は、医薬品や医療機器における基準、医療情報の取り扱いなどを指します。人の命に関わる医療業界では、その有効性や安全性を確保するために厳格なレギュレーションが規定されています。
また、過度な刺激により細胞の応答能が増大することを「アップレギュレーション」、低下することを「ダウンレギュレーション」と表現します。
スポーツ業界のレギュレーション
スポーツ業界で使われる「レギュレーション」は、競技運営における規則や規定を意味します。例えば「2024年6月1日時点で日本国内に在住していること」といった参加資格、「対戦成績が1勝1敗の場合は2試合の総得点で勝敗を決める」といった大会規定、「禁止薬物を使用しない」といった禁止事項などをまとめたものがレギュレーションとなります。
競技ごとに守るべきレギュレーションがあり、公平・公正な競技運営のために欠かせない決まりごとです。仮に違反した場合には選手・チームの出場停止、参加資格の剥奪などの処分が下されることもあります。
建設業界のレギュレーション
建設業界で使われる「レギュレーション」は建築設計の基準を意味します。建物の高さや色、耐震・免震の安全基準など、各地域によって異なる規定が設けられています。建物の設計・建設においては地域ごとのレギュレーションを確認し、その基準に従って進めていく必要があります。
レギュレーションを作成・共有する必要性
一般的にレギュレーションとは「必ず遵守すべき規則」をいいます。業界によっては法律による規制があり、これに背いた場合には法的ペナルティが科されたり組織運営に大きな損害をもたらしたりするおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも適切なレギュレーションを作成し、関係者一人ひとりがいつでも確認できる状態にしておかなければなりません。
法律に関わらない分野においても、レギュレーションの共有によって全員が同じ認識で作業に取り組めるようになり、業務の標準化につなげられます。特に多くの人が関わるプロジェクトでは、全体の統一性を図って仕事の品質を安定させるために、明確な規定・規則を定めたレギュレーションが必須となります。
レギュレーションを効率的に管理する方法
レギュレーションを効率的に管理するにはクラウドツールの活用がおすすめです。
ここではツール活用のメリットとおすすめツールを紹介します。
レギュレーション管理にツールを活用するメリット
クラウドツールを活用するメリットとして「更新しやすいこと」「共有しやすいこと」「検索しやすいこと」が挙げられます。
レギュレーションが増えた場合にはその都度追記し、関係者と情報共有する必要があります。WordやExcelを使って管理することも可能ですが、ツール運用と比べると情報の更新・共有に手間がかかります。この点、クラウドツールなら更新する度に関係者へリアルタイムで通知でき、必要な情報をすぐに届けられます。検索機能が充実しているツールも多く、社員が情報を探す時間と手間を減らせるメリットもあります。
レギュレーション管理におすすめのツール
社内のレギュレーション管理におすすめのツールを3つピックアップしました。
KiteRa Biz
サービスサイト:KiteRa Biz
KiteRa Bizは企業の規程業務を効率化するツールです。社内規程の作成・運用やグループ会社との情報共有、社外関係者とのやりとりなどを一元化できます。KiteRa Bizで管理できる規程は幅広く、就業規則や賃金規程、取締役会規程、販売管理規程、コンプライアンス規程、予算管理規程など各部門の規程に対応できます。ツール導入により規程作業の約70%を削減したデータもあり、大幅な業務効率化につながっています。
| プラン | 料金 | 保管規程数 | 管理者アカウント数 |
|---|---|---|---|
| Free | ¥0(無料) | 2 | 2 |
| Business | 問い合わせ | 50 | 3 |
| Enterprise | 問い合わせ | 無制限 | 10 |
※初期費用が別途必要
Note PM
サービスサイト:Note PM
Note PMは社内のあらゆるナレッジを一元管理できるツールです。社内マニュアルや業務手順書、社内wiki、ノウハウ共有、取引先との情報共有など多様なシーンで活用でき、7,000社以上の導入実績があります。知りたい情報がすぐに見つかる強力な検索機能があり、社員が早急にレギュレーションを確認したいときも瞬時に必要な情報にたどり着けます。作成したページはPDF形式での出力が可能で、ローカル環境にも保存できます。
| プラン | 料金 | ユーザー数 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 8 | ¥4,800/月 | 8 | 80GB |
| 15 | ¥9,000/月 | 15 | 150GB |
| 25 | ¥15,000/月 | 25 | 250GB |
| 50 | ¥30,000/月 | 50 | 500GB |
| 100 | ¥60,000/月 | 100 | 1TB |
| 200〜1000 | ¥120,000〜¥600,000/月 | 200〜1000 | 2TB〜10TB |
※初期費用とサポート費用は0円
※見るだけのユーザーは無料
octpath
サービスサイト:octpath
octpathは弊社が提供しているクラウド型プロセスマネジメントツールです。作業に合わせて順番にマニュアルが表示されるため、ステップや手順が標準化し、安定したクオリティを維持できます。レギュレーションの作成・共有だけでなく、メンバーごとの工数や進捗状況を把握し、業務管理まで行いたい組織におすすめです。octpathのすべての機能を体験していただける無料トライアルをぜひお試しください。
| プラン | 料金 |
|---|---|
| スタンダード | ¥30,000〜/月 |
※初期費用が別途必要
おわりに
レギュレーションとは「規則」や「規制」を意味し、何かに取り組むうえで「必ず守らなければならない決まりごと」をいいます。「ルール」も似た意味を持つ言葉ですが、レギュレーションのほうがより厳格な規則であり、守らなかった場合には法的なペナルティが発生することもあります。ビジネスにおいてはレギュレーションを遵守することが健全かつ公正な組織運営につながります。
本記事ではレギュレーション管理におすすめのツールとして以下の3つを取り上げました。
- KiteRa Biz
- Note PM
- octpath
KiteRa Bizは社内規程の管理に特化したツール、Note PMは社内のナレッジを一元管理できるツール、octpathはレギュレーションの作成から業務管理まで行えるツールです。ツールを選ぶ際にはいくつか気になるものをピックアップし、まずはトライアルやデモを通じて操作性を確認することをおすすめします。